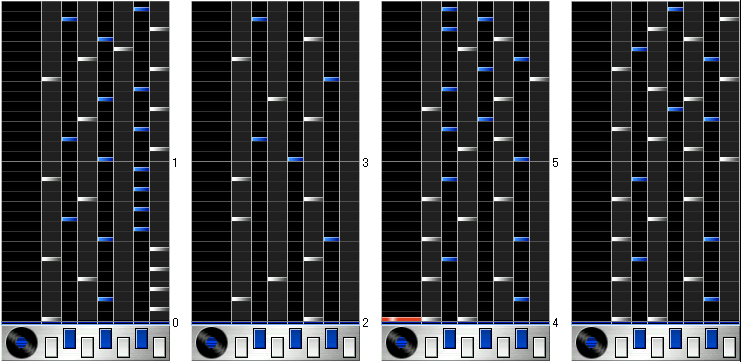
��S�T��@�����e�[�}�FAbyss�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���Q�R���i���j
�s�A�m�̐��������ɔ������Adj TAKA�̊y�ȁB��Փx�I�ɂ����Ɏ荠�Ƃ����Ӗ��������Ă��A��������l�C�������y�Ȃł���B�Ȃ̃^�C�g���ł���uAbyss�v�Ƃ́A�u��Ȃ��n���v�Ƃ����Ӗ������邻�������A�Ȃ̔�������BGA�̕��͋C���猩��ƂƂĂ������̃C���[�W�̂悤�Ɏv����B�Ȃ��AAnother�̕��͂Ƃ���ǂ���ɂ��т������ʂ�������̂́A�����ăN���A�ł��Ȃ����̂ł͂Ȃ��悤���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�������������@
�@�����Ձ�
���Ղɓ����Ă����́A�ȉ��̕��ʁB
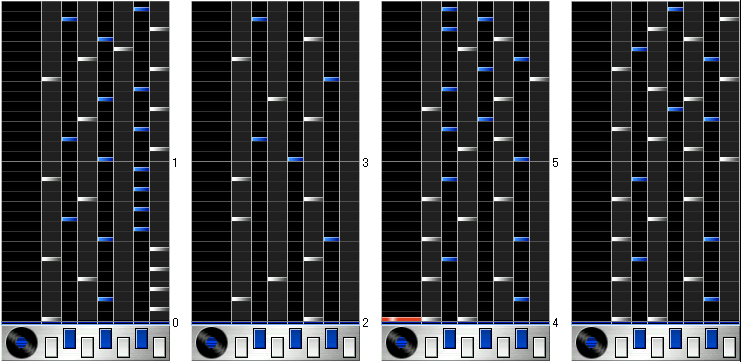
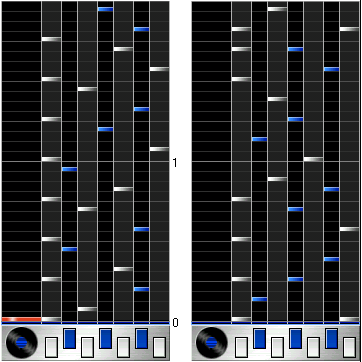
���ɓ�͂Ȃ��Ǝv�����A���ŕ��ʂȂ̂ŁA���ʂ��o�������Ƃ������̂��߂Ɍf�ڂ��Ă����B�^�w�I�ɖ���������z�u�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA������x���ʂ�c�����Ă����A�X���[�Y�Ɏw�������Ǝv���B
�����āA�ȉ��̕��ʁB
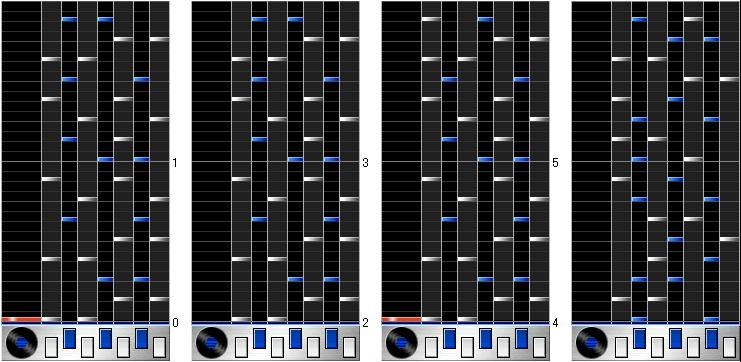
�P�U�����݂ł͂Ȃ��A�W���̂Q���Փ��������ł���Ƃ���ɒ��ӁB�n�C�X�s�[�h�I�v�V���������ăv���C���Ă���l�Ȃ�A���ʓI�ɂ����₷���v���C���₷�����̂Ǝv���邪�A�m�[�}���X�s�[�h�v���C���Ƃ���������镈�ʂ�������Ȃ��B
�@�����Ձ�
�܂��́A�ȉ��̕��ʂ���B
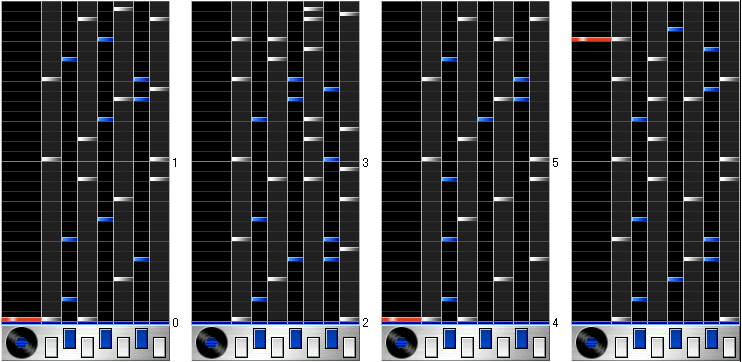
�^�w�͊�{�ʂ�A�P�`�S�Ԃ�����ŒS���B�Ƃ���ǂ���ɏo�Ă���P�U�����A���ɖ��͂Ȃ��낤�B�S���ߖڂ̍Ō�ɏo�Ă���T���V���T�́A�P�U���ł͂Ȃ��R�Q���Ԋu�Ȃ̂Œ��ӁB
�����āA�ȉ��̕��ʁB
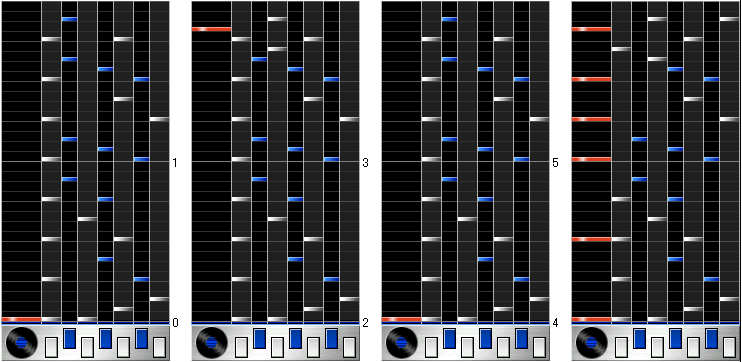
�O���͖��Ȃ��B�R���T���V��U���S���Q�̂P�U���́A�ł���ΉE��P�{�ł������ƁB�㔼�����ɂ��ẮA�f���I�ɃX�N���b�`�������ł��邪�W���ߖڂɊւ��Ă����Ό��Ղ͏[���Ў�ł����������x�̃I�u�W�F�z�u�ɂȂ��Ă���BAnother�o�[�W�����̃N���A��ڎw���l�Ȃ�A�ł�����茮�Ղ͕Ў�ł����悤�ɁB
�@���I�Ձ�
���Ղ̃��}����Ȃ������邱�Ƃ��ł���A���̋Ȃ̓N���A�����R�B���ʂ͊����B�Ō�܂ŋC�����B���Ւ��S�̕��ʂ����A��Փx�I�ɂ͍��܂ł̓�Փx����͈͂̔z�u�ł͂Ȃ��B
��S�S��@�����e�[�}�FKISS ME ALL NIGHT LONG�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���Q�O���i���j
�������NAOKI�̊y�ȁB5th�̐V�Ȃ̒��ł́A���Ȃ�l�C�̂���Ȃł͂Ȃ����낤���B�����āA���Ƃ��̋Ȃ�NAOKI���̋Ȃ̒��ł����߂ĉ̎������{��ł���Ȃ炵���B�]�T��������́A�v���C�����̎����悭���݂��߂ăv���C���Ă݂Ă������������B�Ȃ��A���̋Ȃɂ�Another�͂��邪�A������͂���قǓ�Փx�I�ɂ͕ω��i�V�B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�����������@
�@�����Ձ�
�C���g�������́A�ȉ��̕��ʁB
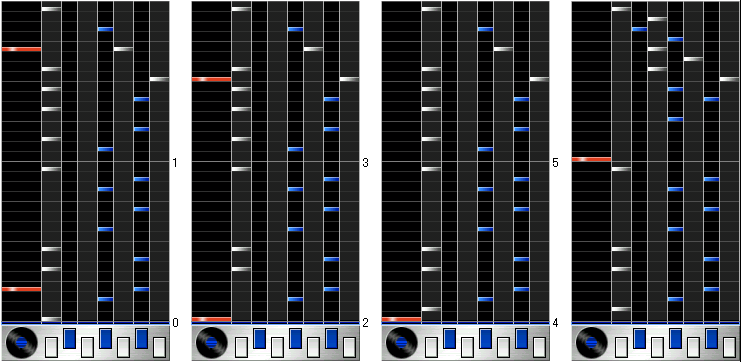
�Ƃ肽�Ăē���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�^�C�~���O���ɓ�V����l�����邩������Ȃ��̂ŁA�Q�l�܂łɋ����Ă݂��BGOOD�������l�́A�����ŕ��ʂ��������ă^�C�~���O���̃C���[�W�g���[�j���O�����Ă݂悤�B�܂��A�n�C�X�s�[�h���x�����グ��̂��悢�B
�@�����Ձ�
�T�r�ɓ�����A�ȉ��̕��ʁB
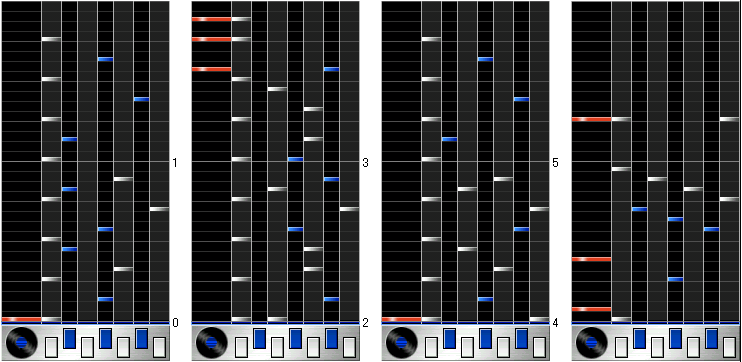
���̕��ʂ͏I�Ղɂ��`��ς��ēo�ꂷ����̂Ȃ̂ŁA�����Ŋ�{���o���Ă����đ��͂Ȃ��B�I�u�W�F�z�u�I�ɂ����ɖ����̂��镔���͂Ȃ����A�����ċ�����S���ߖڂ��A1P���v���C���Ə����Z�������ʂɂȂ��Ă��邩������Ȃ��B2P���v���C�Ȃ�A�X�N���b�`�͉E��ŏ[���J�o�[�ł���̂Ŗ��͂Ȃ��B�܂��A�V���ߖڂ̓^�C�~���O���悭���ɂ߂Ē@���Ȃ���GOOD�A���ɂȂ�̂Œ��ӁB�V���T���R���P�̃p�^�[���́A�Ў�ł��[������̂����^�C�~���O�������Ȃ肪���Ȃ̂ŁA�����܂ł͗���Ń^�C�~���O���ӎ����Ē@���悤�ɂ������B
�@���I�Ձ�
���Ղ���̎������ʂ������B���ʂ͊����B���Ղ��@����l�͂܂��������Ȃ��B
��S�R��@�����e�[�}�FSTILL IN MY HEART�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���P�V���i�j
�U�c�w�V���[�Y�ł͂��Ȃ��݂ƂȂ����ANAOKI�̃n�C�p�[���[���r�[�g�B���W�������̊y�Ȃ̒��ł́A��܂���Ԃ̂��C�ɓ���̋Ȃł��邪�AAnother�o�[�W�����̓�Փx�͂��Ȃ�̂��́B������Ǝ肪�o�Ȃ��Ƃ������Ƃ��낪�����Ȋ��z�����A����ȕ��ʂł��N���A�����Ⴄ�悤�ȋ��҂����̐��ɂ͑��݂���B�ǂ����K�����炠�����܂ł��܂��Ȃ�̂��c�s�v�c�B�B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�����������@
�@�����Ձ�
����قǂ��т������ʂ͂Ȃ��B�����Ă����Ȃ�C���g�������œo�ꂷ��R�E�T�Ԃ̂P�U���p�[�g�B�r���łP�U���������烊�Y���p�^�[�����ω�����_�ɒ��ӂ��āA���ʂ��悭���ĉ����悤�ɁB
�@�����Ձ�
�T�r�ɓ�����A�ȉ��̕��ʁB
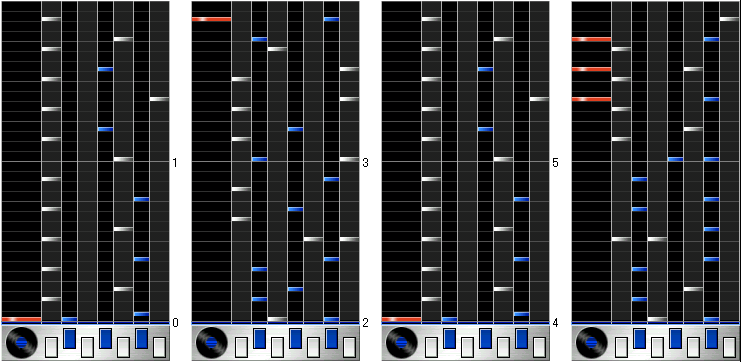
���̕��ʃp�^�[���́A�I�Ղɂ������`���o�ꂷ��B���ӂ��ׂ��͂����P�_�A�W���ߖڂ݂̂ł��낤�B2P���v���C�̏ꍇ�Ȃ�A�X�N���b�`�͂T�E�U�ԂƓ����ɃL�[���X�N���b�`�Ŏ�邱�Ƃ��\�����A1P���v���C���ƃI�u�W�F�ʂ�ɒ@���̂͏������B�����́A����ɂ�����炸�ɂP�Ԃƈꏏ�ɃL�[���X�N���b�`�Ŏ���Ă��܂��̂��悢��������Ȃ��B
�@���I�Ձ�
���Ղ��Ȃ��@����Ȃ�A�I�Ղ͉��̐S�z������Ȃ��͂��B���Ղ̃I�u�W�F�p�^�[���Ƃ͔����ɈقȂ镔�������邪�A�傫���ω��͂Ȃ��đ����I�u�W�F�������������x�Ȃ̂ŁA�C�ɂ������i�ʂ�̊��o�Ńv���C����Α��v�ł���B
��S�Q��@�����e�[�}�Ftabrets�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���P�Q���i�y�j
���_�[�N�ȋȒ��Ƃ�����ۂ̋������C���B�Ȃ̃e���|�͂�⑬�߂ŁAAnother�o�[�W�����ɂ͂����Ƌ����悤�ȕ��ʉ��o���{����Ă���B�������A���̉��o�͈�̂ǂ������Ӗ������̂��낤���c�����̂��₪�点�Ƃ����v���Ȃ��̂����B�B���̂��Ƃ��C�ɂȂ������́A���̊y�Ȃ�Another�o�[�W��������x�v���C���Ă݂Ă������������B������������ł���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�����������@
�@�����Ձ�
�܂��͋Ȃ̑����ɂ��Ă�����悤�ɁB�Ƃ����Ă��A�O���250bpm�̂悤�Ȃ߂��Ⴍ����ȃe���|�ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ɋ����Ǝv���B�����āA�ȉ��̕��ʁB
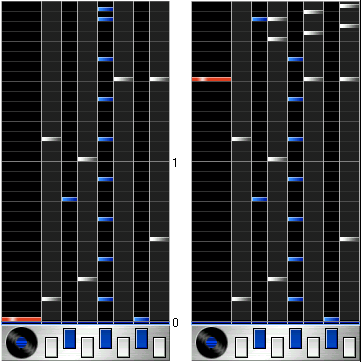
���ƂȂ�̂͂S���ߖڂ̂R���T���V�̂U�A���ł���B�Ȃ̃e���|�������ȂقǁA�ʏ�̂P�U���Ȃ̂��R�A���Ȃǂ̓���Ȕ��Ȃ̂����������Â炭�A������������ʂł͂�����x���ʂ��o���Ă��Ȃ��ƃX���[�Y�Ɏ肪�o�Ȃ��Ƃ������������Ǝv���B�^�w�̊�{�́A�R�Ԃ�����A�T���V���E��Ŏ��B�Q�E�R���T���V�̕�������{�ʂ�̉������ŏ[���B
�@�����Ձ�
���������͂����������Ƃ̂Ȃ������Ɏv����A�ȉ��̕��ʁB
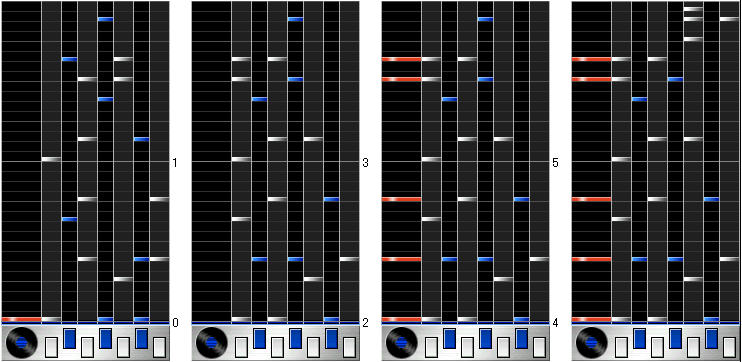
���ہA�P�`�S���ߖڂ͓��ɖ��͂Ȃ��B�����ɃX�N���b�`������ނT�`�W���ߖڂɂ��āA1P���v���C���[�ɂƂ��Ă͂T�E�V���߂��A2P���v���C���[�ɂƂ��Ă͂U�E�W���߂��Ƃ�Â炢�B���ɏ����Ńv���C����ȂǁA���ʂ��܂�Œm��Ȃ���Ԃł��̂悤�ȃI�u�W�F���b�V��������ƁA�ǂ��Ώ����Ă������Ƃ܂ǂ��Ă��܂��āA�ނ��ނ��ƃI�u�W�F�����������ăQ�[�W�啝�_�E���Ƃ����ň��̌��ʂɊׂ��Ă��܂��\��������B�R����̃I�u�W�F�i�Ⴆ�A�P�E�S�Ԃ�Q�E�T�ԂȂǁj�̕Ў蓯�������́A����Փx�̊y�ȂłȂ��Ă����Ȃ�o���p�x�������āA�d�v�ȉ^�w�ł���B���̊y�Ȃɂ��ӂ�ɂ��̉^�w�͐��荞�܂�Ă���̂ŁA�܂����̉^�w����肾�Ƃ������͂�����@�Ɏw�̊��o�����̂ɂ��Ă������������Ǝv���B
�@���I�Ձ�
����قǂ��т������ʂł͂Ȃ��̂����A���������ȉ��̕��ʂ��Љ�Ă������Ǝv���B
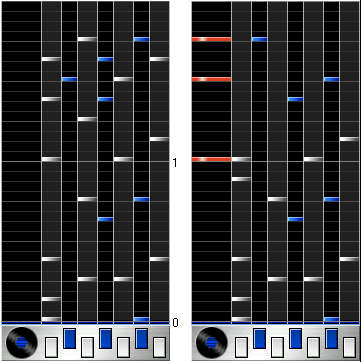
���ڂ���̂͂Q���ߖځB��ł��������R����I�u�W�F������Ƃ����قǓo�ꂵ�Ă���B�P�E�S�E�V���������̂悤�ɁA�Ў�ł͂����Â炢���ʂ͓��R����ł����킯�����A�P�E�V�{�S�Ƃ������́A�P�{�S�E�V�������͂P�E�S�{�V�Ƃ����`�ł����悤�ɐS���������B1P���v���C���[�Ȃ�O�ҁA2P���v���C���[�Ȃ��҂̉^�w�@�����]�܂����B�Ȃ��Ȃ�A���̕��ʔz�u�ɃX�N���b�`������ꍇ�ɁA�^�[���e�[�u�����̎�ŃL�[���X�N���b�`���X���[�Y�Ɏg�����Ƃ��ł��邩��ł���B�ŏ��ɋ������悤�ȂP�E�V�{�S�Ƃ����^�w�@�ł́A�S�ԂƃX�N���b�`���Ɏ��Ȃ���Ȃ炸�A���^�w�ɖ�����������̂ł���B�ȏ�܂��āA���K���d�˂Ă������������B
��S�P��@�����e�[�}�FRadical Faith�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���P�P���i���j
�U�c�w2nd����قڒ�ԂƂȂ��Ă���ATaQ���̃r�b�O�r�[�g�B�O�쏉�o��Voltage�̂悤�ȁA��������ȕ��ʉ��o�͂Ȃ����̂́A���~�U�ɂ��Ă͂��������e�N�j�b�N�̂���I�u�W�F�z�u�ɂȂ��Ă���Ǝv���B���Ȃ݂ɂ��̋ȁAAnother�o�[�W���������݂���̂����A�ǂ����Ă�Another�o�[�W�����̕����ȒP�Ƃ����A���܂܂ł̈Öق̏펯���Ȃł�����B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
�܂��͈ȉ��̕��ʂ������������������B
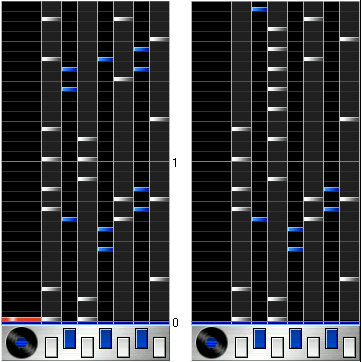
�܂��Ƃ肽�Ăē���z�u�ł͂Ȃ��Ǝv�����A�Ȃ̃e���|�����Ƃ��ƒx�߂Ȃ̂ŃX�R�A�A�^�b�N��_���l�Ȃǂ͂�����ƋC��t�����������ł���B�ǂ����Ă����̂悤�ȍ��ݍ��������ʂ��������Ƃ���Ƃ��ɁA�ł��Ă������Ƃ���Ǝ�̓����������Ȃ��Ă��܂��AGOOD�A���Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��B���������Ǐ�̉��P�@�Ƃ��Ĉ�Ԃ����̂́A�n�C�X�s�[�h�I�v�V�����̃��x�����グ�邱�ƁB5th����n�C�X�s�[�h�I�v�V�������R�i�K�őI�ׂ�悤�ɂȂ�A����ɋȑI�����Ƀn�C�X�s�[�h�̃��x����ύX�ł���̂��B������A���i�̓n�C�X�s�[�h�P�Ńv���C���Ă���l�ł��A���̋Ȃ�I������O�Ƀ��x���Q��R�ɕύX���āA���̎��̋Ȃ�I�ԂƂ��ɂ͂܂����x���P�ɖ߂��Ƃ������Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B���@�́A�ȑI����ʂŁueffector on/off�v�{�^�����������ςȂ��ɂ��邾���B����ƁA�n�C�X�s�[�h���x�������ɕω����Ă����̂ŁA��]�̃��x���ɂȂ�����{�^���𗣂��B��������A�n�C�X�s�[�h���x���A�b�v�ɂ���ĕ��ʂ����₷���Ȃ�A��̓������X���[�Y�ɂȂ邱�ƂƎv���B�m��Ȃ������Ƃ������́A���Ў����Ă݂Ă������������B
�@�����Ձ�
���Ճ��X�g�̃��}�ꕈ�ʂ��ȉ��̂��̂ł���B
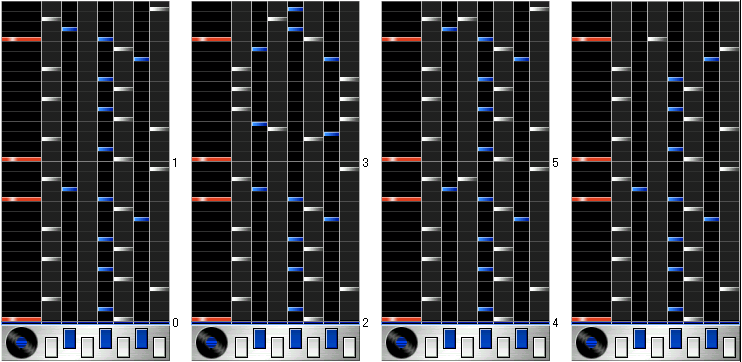
���̕��ʁA�Q�o���v���C���[�ɂƂ��Ă͂�����Ɖ����ɂ����z�u�ł͂Ȃ����낤���B��܂������̕����͂ǂ������ł���B�B�Ȃ̃e���|���x�����߂ɓ��������U���̌��ʂ���┖���i���w�^�ɓ������������BAD���o�Ă��܂�����ł���j�A���Ƃ����Č��ՒS���ƃX�N���b�`�S���Ŋ��S��������ɂ����S�҂ɂ͂��������炢�B�����͂܂��A���������ɏ��S�҂̕��̓X�N���b�`�����Ĕ�����̂���Ԃ����̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�X�N���b�`�����邩��ɂ́A�ł��邾�����Ղ̂������ɏd����u���ė��K���d�˂邱�ƁB�X�N���b�`������ΊȒP������Ƃ����āA�����l�����Ƀv���C���Ă���悤�ł͏��S�҂̈��E�o�ł��Ȃ��B���̓X�N���b�`���������ǁA������͑S��������悤�ɂȂ邼�A�Ƃ����m�ł���M�O�������ăv���C����A���x���A�b�v�͑����Ǝv���B���Ђ�����Ăق����B
��S�O��@�����e�[�}�FSpin the disc�@�U���@�Q�O�O�P�N�T���U���i���j
�U�c�w�V���[�Y�ł͋v���Ԃ�Ȋ���������A�������肵���n�E�X�g���b�N�B���X�N���b�`�����߂̕��ʂ����A�[���������_���ē�Փx�I�ɂ͂���قǍ����Ȃ��B�����҂��ڎw�����~�V�̋ȂƂ��ẮA�V�Ȃ̒��ł͈�ԍœK�ł��낤�B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
�����̕����́A��Փx������߁B�X�N���b�`�̈����łĂ܂ǂ���������Ȃ����A�X�N���b�`�̗��K�ɂ����Ă����̋ȂȂ̂ŁA���ꂢ�ɉ�悤�ɗ��K���悤�B
�@�����Ձ�
���Ղɓ����čŏ��̕��ʁB
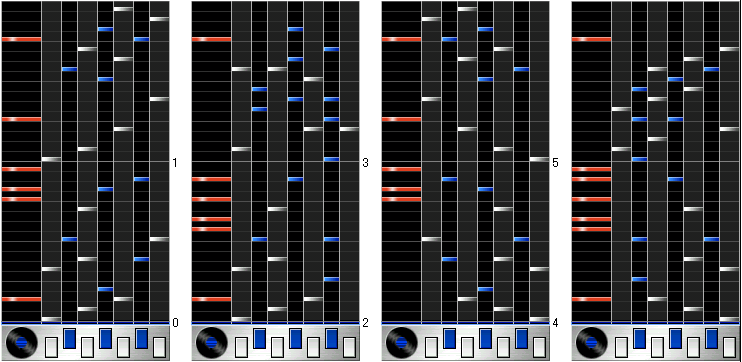
�P�`�R���ߖڂƂT�`�V���ߖڂ́A�X�N���b�`�������ă~���[���ʂƂȂ��Ă���B���������Ӗ��ŁA�S�̂�ʂ��ĂP�o���v���C�ƂQ�o���v���C�ł͓�Փx�I�ȍ��͂Ȃ��Ȃ��Ă���B�����̗��K�̃|�C���g�Ƃ��āA�ł������X�N���b�`��S�����������ł��X�N���b�`�̂��߂Ƀt���[�ɂł���悤�A�^�[���e�[�u���Ɣ��Α��ɂ����i�P�o���Ȃ�E��A�Q�o���Ȃ獶��j�Ō��Ղ������悤�ɁB�����������X�N���b�`�̑����Ȃł́A����͊�{�ł���B�����ɃL�[���X�N���b�`�𑽗p���Ă����Ă��A���ʓI�ɖ����������邱�Ƃ���������ł���B���ɃX�R�A�����C�ɂ����A�N���A������ڎw���̂ł���A�����������o���o�����p���āA�L�[���X�N���b�`�Ŕ����邱�Ƃ��\�ł��邪�A�X�R�A�A�^�b�N��ڎw���l��A�㋉�҂ւ̃X�e�b�v�A�b�v��]�ސl�́A�Ў�ł̌��Ց�����X���[�Y�ɍs����悤�ɂȂ��Ă��������B
�@���I�Ձ�
���ʂ͊��������Ă����������A�������ɏI�ՂɂȂ��Ă���Ɓ��~�V�炵���A�I�u�W�F�����ݍ��������ʂɂȂ��Ă���B�I�ՂŎE���ɂ�����Ƃ����قNj}���ɃI�u�W�F����������̂ł͂Ȃ��āA�Ȃ��i�ނɂ�Ă����Ă����Ƃ����������̑������Ȃ̂ŁA���X�Ɋ���Ă��������ɍU���͉\�B�܂��A���ꂮ����X�N���b�`�̈����������ɂ��Ȃ��悤�ɁB�X�N���b�`�̈������������̋Ȃ̍ő�̃e�[�}�ł��邱�Ƃ�O���ɒu���āA�v���C���Ă������������B
��R�X��@�����e�[�}�FQQQ�@�U���@�Q�O�O�P�N�S���Q�O���i���j
5th�́��~�V�̐V�Ȃ̒��ł���ԊȒP�Ǝv����B���~�V�̐��e��ڎw���Ȃ�A�܂��͂��̋Ȃ����肩����̂��ǂ��ł��낤�B�]�k�ɂȂ邪�A����܂ŇU�c�w�V���[�Y�Ɏ��^����Ă���TaQ���`�̊y�Ȃ̒��ŁA�A�i�U�[�����݂��Ȃ��̂͂��̊y�Ȃ����ł���B�������A4th��DXY!�̂悤�ɁAIR�㔼�ɂȂ��ăA�i�U�[���ւƂȂ�p�^�[�����l������B�����������Ƃ���ƁA���炭����낤�ȁc�B�B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�������������@
�@�����Ձ�
���Ղ̍Ō�̕��ɓo�ꂷ��A�ȉ��̕��ʁB
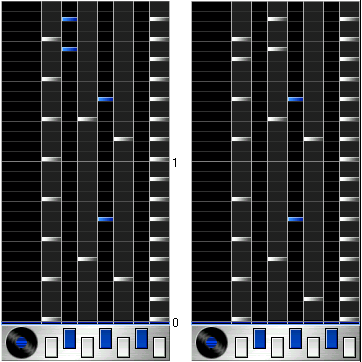
����Ƃ����قǂ̕��ʂł��Ȃ����A�V�Ԃ̃^�e�A�łɒ��ӁBEXPERT���[�h�ł́A������BAD�A���͂�����ƒɂ��B�^�w�͊�{�ʂ�A�P�`�R�Ԃ�����ŁB
�@�����Ձ�
���Ղ̍Ō�ɓo�ꂷ��A�ȉ��̕��ʁB
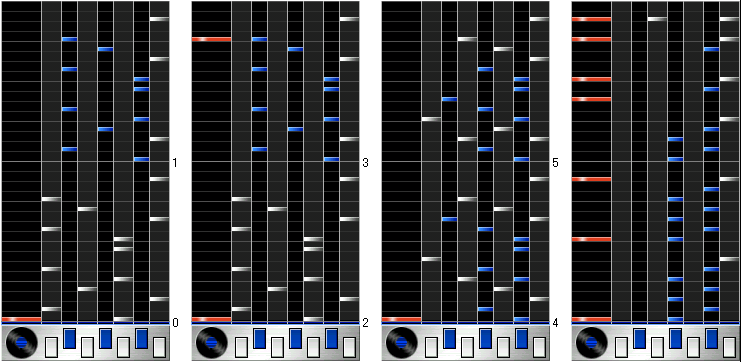
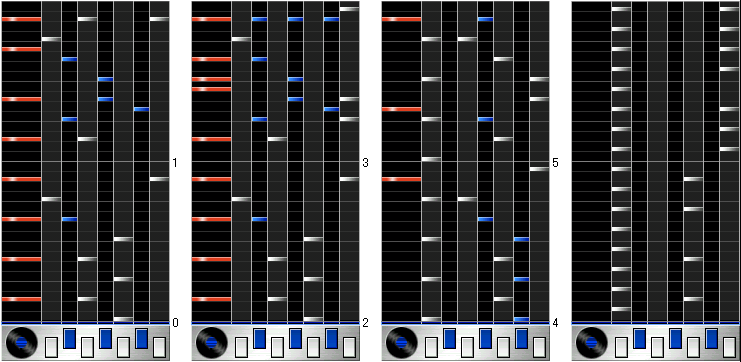
��i�ɂ��ẮA�K�i���ʂƂ͂������Ȃ茩�₷���炯�������Ă���̂ŁA�O�������͖�肪�Ȃ��Ǝv���B�㔼�̂T�E�U���ߖڂ͏��������������Ă��Č��Â炢���������邪�A��{�ʂ�̉^�w�ŏ[����������B�^�C�~���O���悭���ނ��Ƃ��d�v�B���i�͒f���I�ɃX�N���b�`�������ł��Ă�����Ɩ��Ɍ�����B�X�N���b�`�̃^�C�~���O�������ƈ��ł͂Ȃ��̂ŁA�Â����Ă���Ƃ������������ŃQ�[�W������邩������Ȃ��B�܂��A�V�E�W���ߖڂ̃^�e�A�ł��P�U���̗�������{�ɂȂ��Ă���B�X�N���b�`�̒f���ł����ԏł肪�o�n�߂�Ƃ���ɂ��̕��ʂ������Ă�����ƁA�����@��������BAD�A���ɂȂ�\������B���������ď[���Ƀ^�C�~���O�����ɂ߂邱�ƁB
�@���I�Ձ�
���ȕ��ʂ͂Ȃ��̂ŁA��������B�Ō�܂ŋC�����Ƀv���C����A���Ȃ�N���A�͊ȒP�Ȃ͂��ł���B
��R�W��@�����e�[�}�FV�@�U���@�Q�O�O�P�N�S���P�T���i���j
���҂������܂����A5th style�\�Ȃ̍œ�ւƂ̌Ăѐ��������̋Ȃ̍U�����|�[�g�����������B���ʂɂ��ẮA���������Q�ƁB���|�[�g�����̕��ʂ����ɂ��ēW�J���Ă����̂ŁA���ʂ������ɂȂ�Ȃ��炨�ǂ݂������������v���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�����������������@
�@�����Ձi�P�i�ڑ�P���߁`�U�i�ڑ�T���߁j��
�P�i�ڂ���Q�i�ڂ܂ł͉��̖����Ȃ����낤�B�����܂ł͏��Ȃ��Ƃ��t���R���{��ڎw�����ƁB�����܂Ŋ����ɒ@����A�Q�[�W�͂W�O���ȏ�ɂȂ��Ă���͂��B�ȉ��ł̉ۑ�́A���̃Q�[�W�������Ɉێ����邩�ł���B
�R�i�ڑ�S���߁A�P�o���v���C���[�ɂƂ��āu�P�E�R�E�V�{�r�v���ǂ���邩���ۑ�ɂȂ��Ă���B�����Z�����Ȃ邩������Ȃ����A�P�ԂƃX�N���b�`������ŁA�R�ԁE�V�Ԃ��E��Ŏ��A����ɑ����T�ԂɂȂ��̂����A�R�Ԃ��E��e�w�A�V�Ԃ��E���w�Ŏ��ƁA�T���U�ɃX���[�Y�ɂȂ��₷���͂��B���Ȃ݂ɂQ�o���v���C�Ȃ���ɖ��͂Ȃ��B���ꂩ�瓯������U���߁A�V���U���S���E���{�ŃX���[�Y�ɏo���Ȃ��Ƃ����ŃQ�[�W�����炷���ƂɂȂ�̂ŁA�[�����K���Ă������ƁB�ȍ~�A�T�i�ڒ��Ղ܂ł͖��Ȃ��ł��낤�B
�T�i�ڑ�U���߂��A���悢�悱�̋Ȃ̃��C���t���[�Y�̓o��ł���B�P�o���v���C�ɂ͓��ɖ��ƂȂ镔���͂Ȃ��͂������A�Q�o���v���C�ɂƂ��āA�U�i�ڑ�P���߂̂悤�ȕ��ʂ͏������B���肾���Ō��Ղ����̂͂��Ȃ茵�������A���Ƃ����ĉE��Ō��Ղ������X�N���b�`�����̂��������B�����̓X�N���b�`�A�������͌��Ղ̂ǂꂩ�����Ă��܂��̂������ł��낤�B�X�N���b�`������Ȃ�Ό��Ղ͑S������B���Ղ�����Ȃ�A�u�T�E�V�{�r�v�̂T�Ԃ�����B�ǂ����Ă��S����肽���Ƃ����~����Ȃ��Ȃ��́A�E��Łu�T�E�V�{�r�v������悤���K���邱�ƁB
�@�����Ձi�U�i�ڑ�U���߁`�X�i�ڑ�S���߁j��
���炭�K�i���ʂ��������A���ǂ���Ƃ����V�i�ڑ�Q���߂́u�P���Q���R���S���T���U���V���r�v���炢���Ǝv���B�L���C�ɒe�����Ȃ��Ȃ��Ă���������A�ł�������肱�ڂ��Ȃ��悤�ɁB��肱�ڂ��Ȃ��悤�ɁA�Ƃ����̂́ABAD�ł��������献�Ղ�@�����ƁB�����@������POOR�ōς܂����͂邩�ɃQ�[�W�̌��肪�Ⴄ���炾�B�܂��A�W�i�ڑ�S���߂̗��Œn�т��X�J��������ƈ�C�ɃQ�[�W�������̂ŁA�m���ɒ@�����ƁB
�����ĂW�i�ڑ�T���߂���Ăу��C���t���[�Y���o��B��{�͏��ՂŏЉ���@�����Ƃ܂��������������A���Ղɔ�ׂ�Ƃ����Ԕ�ꂪ�o�Ďw�̓������݂��Ȃ肪���ł���B�����͉䖝�ǂ���A���Ղ��Q�[�W�U�O�����x�Ŕ�������N���A�͖ڑO�ł���B�Ȃ��A���ՍŌ�̂X�i�ڑ�S���߂́A�S���V���S�̊K�i���ʂ��o�ꂵ�Ă���B�����ő�~�X���������Ȃ��悤�ɁB
�@���I�Ձi�X�i�ڑ�T���߁`�P�O�i�ڑ�R���߁j��
����ł����Ƃ���ɏP���������Ă���P�U���A�ł����A���ՂŏЉ���悤�ȓ���I�u�W�F�z�u�͂Ȃ��B������ł��������Ƃ���A�w�̔��ɂ�铮���̓݉����v�����ȏ�ɃQ�[�W�ɋ����Ă���B�w�̔���h�����@�Ƃ��ẮA���Ղ̋��ł��T���邱�ƁB������I�u�W�F���P�Q�V�Q�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��y�ȂȂ̂ŁA�ŏ�����C���������ĂƂ�������ƁA���Ƃ������Ȃ��ł��낤�B�Ō�̕����̂��߂ɑ̗͂��������Ă����悤�ɁB���ꂩ�炱��͋ȑS�̂�ʂ��Č����邱�Ƃ����A���C���t���[�Y�ɓo�ꂷ��P�U���̘A�ł́A���ʂ��悭���ĉE�������̂����������̂��ɒ��ӂ��Ē@���悤�ɁB������ԈႦ�邾����BAD�A���B���ɏI�Ղł�BAD�A���͖����B�S���I�ɂ��܂����Ă��܂��Ă��Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���ʂ͂悭���Ē@���悤�ɂ��悤�B