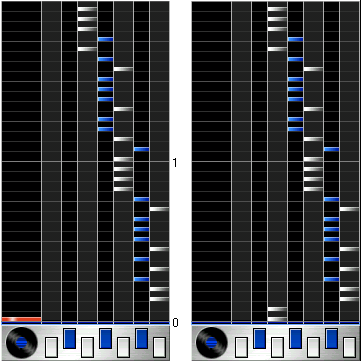
第37回 研究テーマ:Macho Gang 攻略 2001年4月10日(火)
ⅡDXsubstreamにて初登場。HOUSEというよりはテクノ色が濃い感じがするが、テクノ系楽曲にありがちな重苦しい雰囲気はなく、けっこうノれる曲だと思う。難しいと思われる譜面は最初のうちだけで、後半で充分挽回がきく譜面なので、クリアするのは難しくない。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★>
<序盤>
序盤に登場する、以下の乱打譜面。
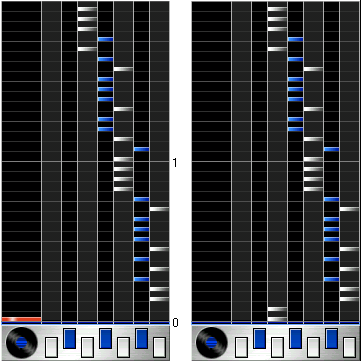
とりたてて厄介というほどではないが、タテの連打なのでタイミングを外すとすぐにBAD地獄に陥ることになる。また、空打ちにも要注意。複数の鍵盤につながるタテ連打なので、空打ちPOORからBAD連発になった場合、修正がききにくいからである。
<中盤>
中盤の難関譜面は、以下のもの。
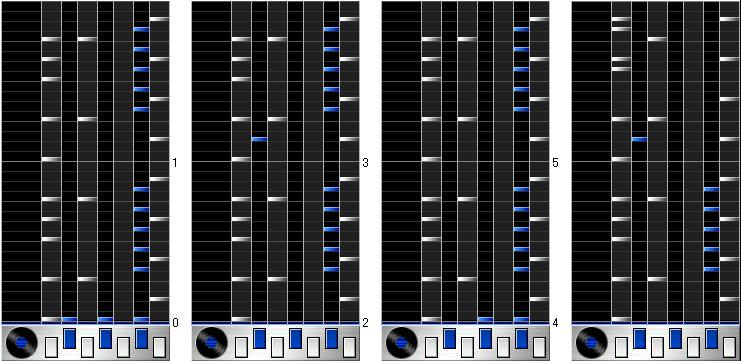
1~3番の基本リズムと同時に6・7番の16分譜面をこなすわけだが、運指法は言うまでもなく6・7番を右手で。右手と左手でタイミングが異なる運指になるので、どちらかの手にもう片方の手がつられないように。もっとも、この難所を超えれば後はかなり簡単な譜面なのだが。。
<終盤>
上で紹介した譜面の変化型が登場するのだが、上の譜面よりも簡単なので心配はない。はっきり言って終盤だけ全部取れればこの曲はクリアしたも同然。前半が苦手だという人は、後半の攻略に力を入れるのもクリアの手である。
第36回 研究テーマ:S.O.S.攻略 2001年4月7日(土)
ⅡDX2ndにて初登場の楽曲。なんとも脳天気な雰囲気が満ちているが、難易度的には決して低くない。4th style登場の際に姿を消したが、3rdにてD.E.リミックスバージョンが登場した。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★☆>
<序盤>
イントロ部分にあたる、以下の譜面。
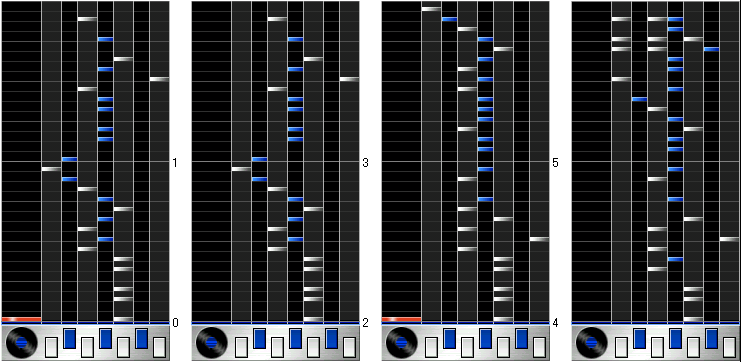
全体にわたって階段譜面となっているが、特に難しいのが8小節目であろう。1~3番を左手で、4~7番を右手で取るのはいうまでもないと思うが、1・3番のリズムパートと同時に登場する、「4→4→6→5→4→4」の階段譜面を叩くとき、左手のタイミングがずれやすいので注意。この譜面は曲の最後にも登場するので、ここでのミスを最小限に押さえるよう、充分練習を積んでおこう。
<中盤>
この曲で難しい譜面といえば、上で挙げた部分だけなので、中盤では細かいミスをしないよう、気を付けてプレイしよう。中盤で少し注意がいる譜面は、サビ部分の最後に登場する以下の乱打譜面。
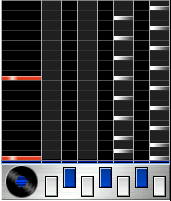
単純な16分乱打ではなく、最初の3拍は24分間隔となっている。ここは譜面間隔が込み合っている部分なので、タイミングをよくとらえて叩かないとBAD連発になるので要注意。特に同じ譜面が終盤直前にも登場するが、終盤直前でミスが重なるとクリアが難しくなるので、この部分の叩き方もマスターしておきたい。
<終盤>
序盤で紹介した譜面とまったく同じ譜面が登場するので、説明は割愛する。ただし、序盤で挙げた8小節で曲が終了するので、ここでの大ミスは命取り。そうならないためにも、序盤の譜面でミスをしないよう、充分な練習を積むこと。
第33回 研究テーマ:PARANOIA MAX 攻略 2001年4月5日(木)
ⅡDXsubstreamの隠し曲扱いだった楽曲。かなり古いので、いまさら出現条件を書くことはないと思うので割愛する。DDR2ndにも収録されており、一時期稼働していたDDRとのセッションプレイ版(CLUB VERSION)がけっこう熱かった。あ~あ、CLUB VERSION復活しないかな…。。さて、原曲の方は簡単すぎるので、このページではAnotherバージョンの攻略について書こうと思う。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★>
<序盤>
最初のうちは、それほど降ってくるオブジェも多くなく、もとよりBPMが高いからけっこうやりやすい譜面なのではないかと思う。オブジェの落下スピードに慌てず、落ち着いて譜面を見ればフルコンボも難しくない。
<中盤>
降ってくるオブジェの数もだんだん多くなってくるが、まだまだ大したことはない。特に苦労させられる譜面の配置もなく、ここもさらりとこなしていきたいところ。スピードが速いので、8分刻みと16分刻みをよく見極めて叩くこと。
<終盤>
ちょっとしたオブジェラッシュの場面。以下の譜面をご覧いただきたい。
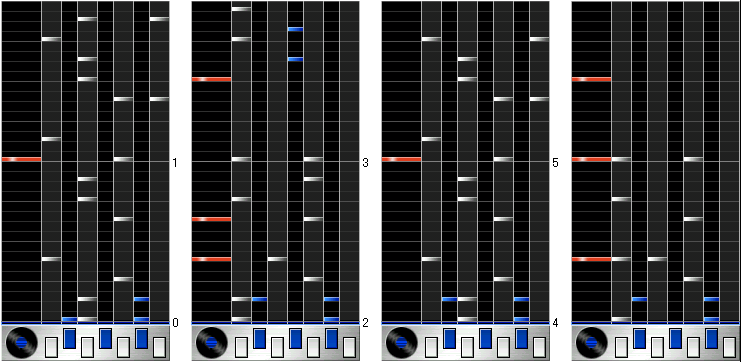
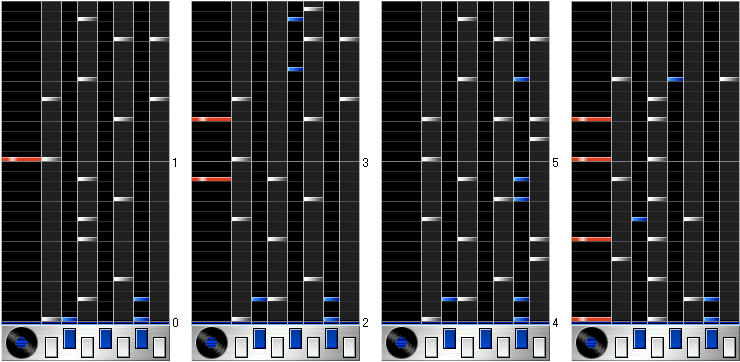
ところどころにスクラッチも混ざっていて、少しいやらしい譜面かもしれないが、前半8小節はそれほどの難易度ではない。後半8小節は手が忙しい譜面となっている。運指の基本は、1~4番を左手で、5~7番を右手で。隣り合う白鍵と青鍵の同時押しがところどころに登場するので、すぐ反応できるように譜面でイメージトレーニングをしておくのもよい。
第32回 研究テーマ:dong-tepo No.1 攻略 2001年4月3日(火)
ⅡDX2ndにて隠し曲として登場。ⅡDX史上初の難易度★×7の楽曲である。出現条件は特別ボーナス点を除いて195000点以上のスコアでいずれかの曲をクリアするというものであった。この条件、★×1の曲でトライすれば比較的簡単にクリアできるのだが、出現させたあとが大変であった…今でもけっこう難しいと感じることがある。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★>
<序盤>
導入部を抜けたあとの、以下の譜面。

テクノというジャンルの特性上、繰り返し譜面が基本なのだが、いかんせんかなり忙しい譜面となっているので、初めのうちはどこかの鍵盤を無視した方がやりやすかろう。1P側プレイでは特に無視オブジェは見あたらなそうだが、2P側プレイでは2つ目のスクラッチあたりを無視できるかもしれない。運指の基本は1~3番が左手、4~7番が右手である。
さらに、上の譜面の直後に登場するのが以下の譜面。
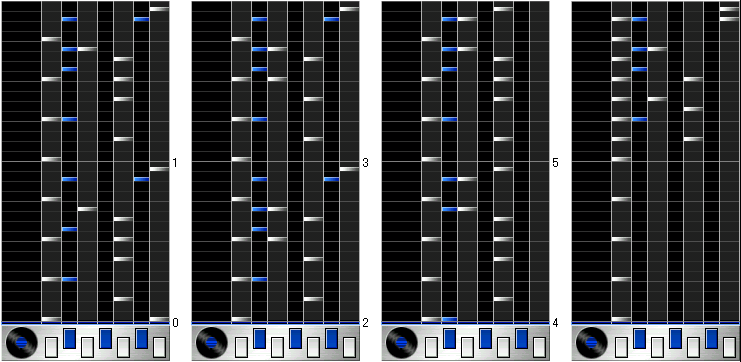
1・2番を左手、残りを右手で。右手のカバー範囲が広いと思うかもしれないが、それほど忙しい譜面ではないので、何とかなるはずである。8小節目が少し厄介かもしれない。少しでも1番のタイミングがずれてしまうと、BAD連発になるので、できれば1番だけを左手で打って、残りを右手で全部カバーするようにしたいところ。リズムパートとメロディパートを分離して、タイミングの混同を防ぐためである。
<中盤>
中盤の終わり際にでてくる、以下のような譜面。
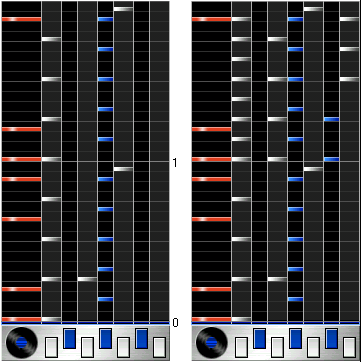
スクラッチが多く、少しいやらしい譜面。1P側プレイなら1番とスクラッチを左手、残りを右手で1~3小節目を叩く。それほど難しくないはずだが、2P側プレイだと少し話が違う。できれば、鍵盤は全部左手で取って、右手はスクラッチに集中すること。最後の4小節目については1P側・2P側共に厄介だが、スクラッチを無視して鍵盤だけに集中するのもひとつの手である。その場合は1・3番を左手で、4~7番を右手で取ることはいうまでもないだろう。ここで無理して全部オブジェを取ろうとすると鍵盤のスカしなどで大きくゲージを減らす可能性が高いので、取れる分だけを無理せず取るように。この譜面のあとも少し忙しい譜面が続くので、クリアを目指すなら全部取ることよりもゲージを残すことを考えること。ここを抜けた時点で50%も残っていれば、ほぼクリアできたと言っていいと思う。
<終盤>
中盤でも出てきた譜面配置の変化型譜面が登場。譜面は割愛するが、ところどころに出てくるスクラッチもできるだけ無視しないで、ここはパーフェクトを目指したいところ。なお、最後の最後で、曲が切れたあとにもスクラッチ譜面が落ちて来るという、ちょっとした意地悪な演出もあるので、最後まで気を抜かないように。
第31回 研究テーマ:.59 攻略 2001年4月1日(日)
ⅡDX2ndから登場した、今でもけっこう人気のある楽曲。それまで主流であった「タテの連打」から、7つの鍵盤を広く使った「ヨコの連打」系の曲をⅡDXにもたらした、きっかけの曲とも言える。同一フレーズのくり返しが多いことから、テクノ系楽曲として分類されるようだが、曲調はテクノのような無機的でリズミックな感じはなく、むしろメロディアスである。2ndが登場した当時は、この曲をぜひとも攻略したいと思ったプレイヤーはかなり多かったのではないだろうか。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★>
<序盤>
イントロの後に登場する、この曲の基本フレーズが以下の譜面である。
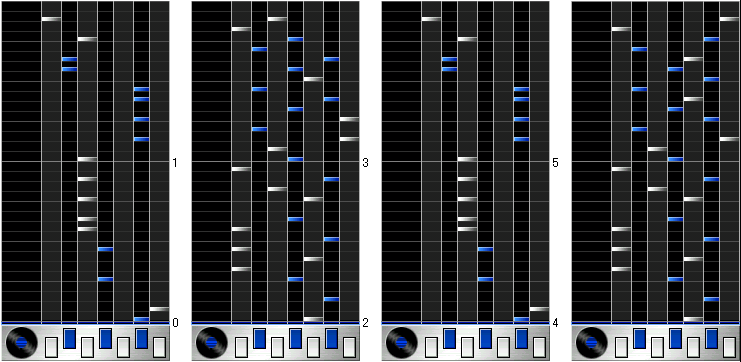
3・4小節目や、7・8小節目のように広い範囲でオブジェが降ってくるのがこの曲の特徴でもあった。しかし、最近登場するヨコの連打の曲に比べればかなり易しい方で、運指は右手と左手を交互に使うことで簡単に抜けることができる。参考までに、やまきの7・8小節目の運指法を以下に示しておく。(白が右手、黄色が左手である)
5→6→4→1→5→1→6→1→4→5→3→6→1→
4→3→7→2→6→4→5→2→6→4→5→2→6→1→7
また、この後に登場するのが以下の譜面。
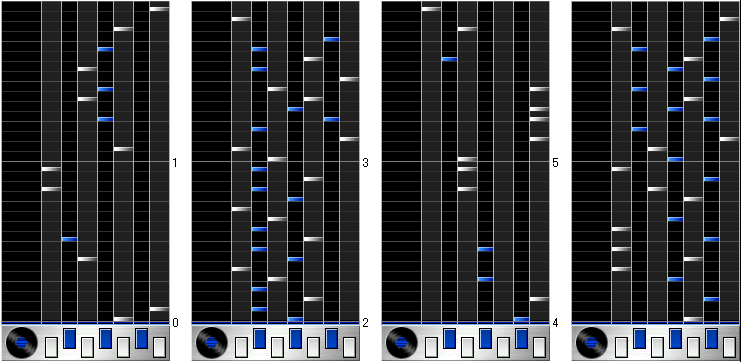
3・4小節目が少し違った譜面配置であるが、ここもやはり上で説明したとおり、左手と右手を交互に使うことで抜けられる。7・8小節目は、上の譜面の7・8小節目と同じなので、これも説明はいらないであろう。なお、このような右手と左手の交互16分押しは焦って叩くとタイミングがずれやすいという欠点もある。できるだけ落ち着いて、「右・左・右・左…」といったカンジで頭でタイミングをつかめば、キレイに叩けるようになる。
<中盤>
中盤はリズムパートが中心。ここは特に説明は不用であろう。強いて注意点を挙げるとすれば、途中に登場する、1番の32分連打はスカしやすいのでしっかり叩くこと。
<終盤>
序盤に登場したメロディ譜面に、1番の基本4拍リズムが加わった譜面が登場。序盤がしっかり叩ければ、何の問題もない譜面となっているが、16連オブジェの途中にスクラッチがからんでいたりするので、ここは注意が必要かもしれない。なお、曲の最後は若干BPMが遅くなるので、オブジェを判定ラインに引きつけてゆっくり目に鍵盤を取ること。もっとも、BPM変化手前まで100%を保っていれば、よっぽど最後で鍵盤をスカさない限りはクリアできるはずであるが。
~最後に~
この曲は、初心者のステップアップに非常に適した曲である。初心者のみなさまは、この曲のクリアを目標にがんばっていただきたく思う。