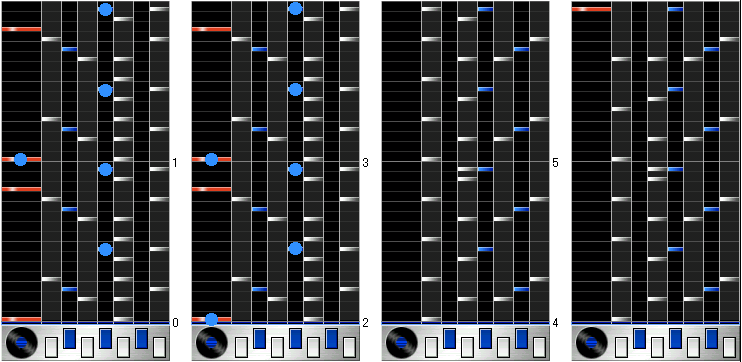
戞俁侽夞丂尋媶僥乕儅丗DXY!丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧俁侾擔乮搚乯
偙傟偧傑偝偟偔僥僋僲丄偲偄偭偨姶偠偑偡傞丄4th style廂榐偺怴嬋偺拞偱傕傕偭偲傕擄堈搙偺崅偄嬋丅儓僐楢懪偺嬋偑棳峴偟偰偄傞拞偱丄偑偭偪傝偲偟偨愄側偑傜偺僞僥楢懪偺僷乕僩傕懚嵼偟丄偨偩偺儕僘儉僷乕僩埲奜偵傕棳傟傞傛偆側僔儞僙僷乕僩偺奒抜晥柺傕搊応偟丄帩偪偆傞僥僋僯僢僋偺慡偰傪巊傢側偄偲峌棯偼擄偟偄偲巚傢傟傞丅桞堦偺媬偄偲偄偊偽丄僥僋僲偲偄偆僕儍儞儖暱偺偣偄偱孞傝曉偟晥柺偑懡偄偲偙傠偱偁傠偆丅偙偺偍偐偘偱丄晥柺傪嶌傞偺偼娙扨偱偁偭偨乮敋乯丅峌棯偵偼偄偔傜巊偭偨偙偲偐乧乮椳乯丅丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仛仛亜丂
丂亙彉斦亜
摫擖晹暘偼偦傟傎偳擄偟偔偼側偐傠偆丅摫擖偐傜嵟弶偺僼儗乕僘傪敳偗偨屻偵搊応偡傞丄埲壓偺晥柺偑偐側傝栵夘偱偁傞丅
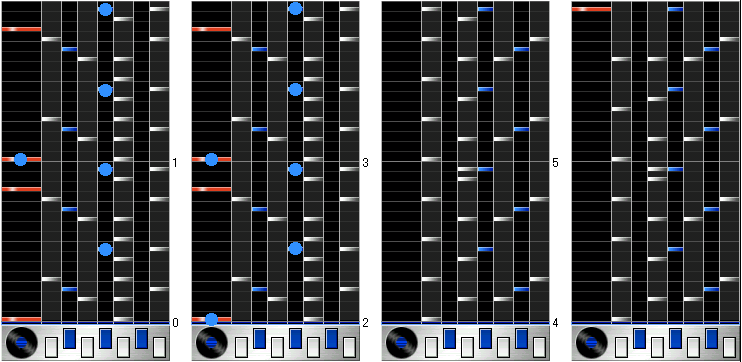
侾乣係彫愡栚偼僗僋儔僢僠傕偐傜傫偱偄偰丄偐側傝擄堈搙偺崅偄晹暘丅偙偙偱戝偒偔僎乕僕傪尭傜偡恖偑傎偲傫偳偩偲巚偆丅傛偭傐偳姷傟側偄偲慡晹偺僆僽僕僃傪庢傞偺偼柍棟偩偲巚偆偺偱丄柍帇偟偰傕栤戣偺側偝偦偆側僆僽僕僃偵悈怓偺仠傪偮偗偨丅偼偭偒傝尵偭偰侾乣係彫愡傑偱偼傑偭偨偔摨偠晥柺偺孞傝曉偟偩偐傜丄楙廗傪廳偹傟偽偡偖偵塣巜傕儅僗僞乕偱偒傞偱偁傠偆丅嵍庤偱乽俁仺俀仺侾乿偺奒抜傪丄塃庤偱俆丒俈斣傪庢傞丅僗僋儔僢僠偼丄尩枾偵偼僞僀儈儞僌偑偢傟偰偄傞偺偩偑乽俁仺俀仺侾乿偺奒抜晥柺傪庢傞偲偒偵丄侾斣偲摨帪偵僉乕仌僗僋儔僢僠偱庢偭偰偟傑偍偆丅乮俀俹懁傉傟偄側傜丄俈斣偲堦弿偵庢傞乯偪側傒偵丄忋偱帵偟偨柍帇僆僽僕僃埲奜傪慡偰庢偭偨応崌丄僎乕僕偼偩偄偨偄俇侽亾掱搙巆傞丅偝偰丄俆乣俉彫愡栚偺曽偼丄係乣俈斣傪塃庤偱丄侾丒俁斣傪嵍庤偱庢傞丅偙偪傜偺曽偑塣巜偑儔僋側偺偱丄偙偙偱偟偭偐傝僎乕僕傪夞暅偟偰偍偒偨偄丅嵍庤扴摉偺晥柺偼侾斣偲俁斣偺岎屳俉攺墴偟偑婎杮側偺偱丄塃庤偺摦偒偵偮傜傟側偄傛偆偟偭偐傝婎杮儕僘儉傪崗傓傛偆偵丅
丂亙拞斦亜
偼偭偒傝尵偭偰丄拞斦慡懱偵傢偨偭偰僎乕僕夞暅僝乕儞偲側偭偰偄傞丅晥柺偼妱垽偡傞偑丄偙偺拞斦偵偼侾丒俈斣偺僞僥侾俇暘楢懪偑搊応偡傞丅偙偙傪偍傠偦偐偵偡傞偲偐側傝僎乕僕傪尭傜偟偰偟傑偆偺偱丄偙偙偩偗拲堄偟偰扏偔偙偲丅側偍丄侾俇暘楢懪傪敳偗偨捈屻偼偄偐偺傛偆側晥柺偑搊応偡傞丅
丂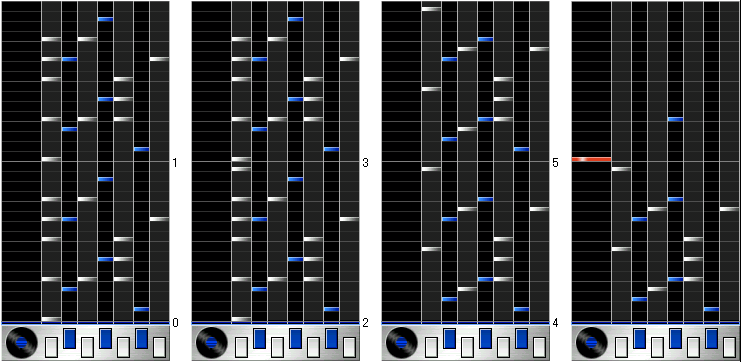
侾乣係彫愡栚偼傑偭偨偔栤戣側偟丅俆乣俉彫愡栚偵偮偄偰偼丄侾乣俁斣偑嵍庤丅乽俀仺俁仺係乿偺奒抜傪嵍庤偱庢傞曽朄傕偁傞偑丄偦偺晹暘偵懕偔俆斣偺俁攺偵偮側偘傗偡偔偡傞偨傔偵係斣偩偗偼俆斣偺傾僞儅攺偲摨帪偵塃庤偱庢偭偨曽偑傗傝傗偡偄偐傕偟傟側偄丅偳偆偄偆傗傝曽偵偟傠丄偙偙傪敳偗傞傑偱偵僎乕僕偼俉侽亾埲忋偵偟偰偍偒偨偄丅
丂亙廔斦亜
偙偺嬋嵟戝偺儎儅応晥柺偑埲壓偺傕偺丅
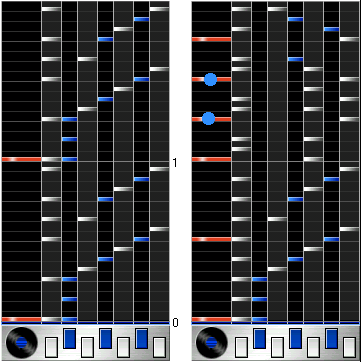
侾俹懁僾儗僀偺応崌側傜丄嵍庤偱庢傞偺偼僗僋儔僢僠偲侾斣偺傒丅偁偲偼塃庤偩偗偱庢傞偙偲丅乽俀仺俁仺係仺俆仺俇仺俈乿偺奒抜偑庢傝偯傜偄偲偄偆恖偼丄俀僆僽僕僃摨帪墴偟偱乽俀丒俁仺係丒俆仺俇丒俈乿偺俉暘墴偟偱柍棟傗傝敳偗偰偟傑偍偆丅彮偟偱傕僞僀儈儞僌偑偢傟傞偲俛俙俢偑弌傞偺偱丄僐僣偲偟偰偼摨帪墴偟偱敳偗傞尞斦偲尞斦偺娫偱摨帪墴偟丅俁俀暘偺僘儗偑惗偠傞偑丄僗僐傾傾僞僢僋傪慱偆側傜偙偺媄弍偼儅僗僞乕偡傋偒偱偁傠偆丅側偍丄係彫愡栚偵偼柍帇僆僽僕僃傪帵偡悈怓偺仠偑晅偄偰偄傞僗僋儔僢僠傕斾妑揑娙扨偵庢傟傞偼偢丅偙偙偼柍帇偣偢慡晹偺晥柺傪庢傝偵偄偙偆丅側偍丄俀俹懁僾儗僀偺恖側傜偽丄嵍庤偱庢傞偺偼侾斣偲俀斣偺尞斦丅偦傟埲奜傪塃庤偱丅俁彫愡栚丄奒抜晥柺偺搑拞偵搊応偡傞僗僋儔僢僠偼柍帇偟偰傕偐傑傢側偄偑丄忋偱傕弎傋偨摨帪墴偟偺媄弍傪巊偊偽丄乽俇丒俈亄俽乿偺僉乕仌僗僋儔僢僠偱庢傞偙偲傕偱偒傞丅係彫愡栚偵偄偨偭偰偼丄傕偼傗慡晹偺僆僽僕僃傪庢傝偒傞偺偼帄擄偺嬈丅偙偙偼偍偲側偟偔悈怓偺仠偱揾偭偨僗僋儔僢僠偼柍帇偟偰偟傑偍偆丅偪側傒偵僋儕傾偺栚埨偲偟偰偼丄偙偺晹暘傪敳偗偨偁偲偺晥柺傪慡晹庢傟傞傕偺偲壖掕偡傟偽巆傝僎乕僕係侽亾掱搙偱傕廩暘僋儕傾壜擻丅媡偵尵偊偽丄偙偙傪敳偗偨屻傕偐側傝偺検偺僆僽僕僃偑崀偭偰偔傞偲偄偆偙偲偵側傞偑乧丅丅傗傑偒偺応崌偼丄俀俹懁僾儗僀偱僗僋儔僢僠傪俀偮柍帇偟偰丄偙偺晹暘傪敳偗偨偁偲偺僎乕僕巆検偼暯嬒偱俉侽亾偔傜偄丅偪側傒偵棟榑抣偼俋侽亾側偺偩偑丄枹偩偵払惉偼偱偒偰偄側偄丅偝偰丄偙偺晹暘傪敳偗偨偁偲偺晥柺偼妱垽偝偣偰偄偨偩偔偑丄偔傟偖傟傕婥傪敳偐偢偵丅棊偪拝偗偽寛偟偰擄偟偄攝抲偱偼側偄丅僆僽僕僃偺検偵嬃偐側偄偱丄怲廳偵傂偲偮偢偮偟偭偐傝庢偭偰偄偙偆丅慡晹庢傟傟偽丄偩偄偨偄係侽亾偼夞暅偱偒傞偼偢丅
丂乣嵟屻偵乣
4th偺嵟擄娭偲偄偆偙偲偱丄偐側傝挿傔偺婰帠偵側偭偰偟傑偭偨偑丄忋偱嫇偘偨晥柺埲奜偼庢傝棫偰偰擄偟偔側偔丄婎杮揑側媄弍偩偗偱忔傝墇偊傜傟傞晥柺偱偁傞丅弶怱幰偵偲偭偰偼尩偟偄嬋偐傕偟傟側偄偑丄拞媺幰埲忋偺恖偼偤傂偲傕僠儍儗儞僕偟偰偄偨偩偒偨偄偲巚偆丅
戞俀俋夞丂尋媶僥乕儅丗250bpm丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧俁侽擔乮嬥乯
beatmania巎忋丄嵟傕崅偄俛俹俵傪帩偮妝嬋丅偙偺嬋偺嫢埆偝偼丄僴僀僗僺乕僪僾儗僀偵偍偄偰業尒偝傟丄側偵偟傠偁傑傝偵崅懍側僆僽僕僃僗僋儘乕儖側偺偱丄偪傚偭偲栚傪棧偡偲偮偄偰偄偗偢偵儃儘儃儘偵側偭偰偟傑偆丅偟偐偟丄僲乕儅儖僗僺乕僪僾儗僀偵偍偄偰偼乽偙偺嬋偺偳偙偑仛亊俈側傫偩両両乿偲偄偆傎偳娙扨丅弶怱幰偺曽偱偁傟偽丄偙偺嬋傪僾儗僀偡傞応崌偵僆僾僔儑儞偱僴僀僗僺乕僪僾儗僀傪偮偗側偄偱慖嬋偡傟偽廩暘偱偁傠偆丅偟偐偟丄拞媺埲忋偺曽偱丄乽偦傫側偦偺応偟偺偓偺傛偆側峌棯曽朄偱偼丄僆儗偺僾儔僀僪偑嫋偝側偄両両乿偲偍巚偄偺傒側偝傑偺偨傔偵丄僴僀僗僺乕僪僾儗僀偱偺峌棯偵偮偄偰彂偙偆偲巚偆丅偪側傒偵偙偺嬋傕塀偟嬋偱偁偭偨丅弌尰曽朄偼乽偳偺嬋偱傕偄偄偐傜丄侾俋枩俀侽侽侽揰埲忋庢偭偰僋儕傾偡傞乿偑掕愢偺傛偆偩偑丄僐僫儈偺敪昞偱偼丄摼揰忦審偼傕偭偲嵶偐偄揰悢偱偁偭偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅乮侾俋枩侾丠丠丠揰偩偭偨側乧傛偔妎偊偰側偄偭偡丅丅乯
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仛乮僴僀僗僺乕僪乯乛仛仛乮僲乕儅儖僗僺乕僪乯亜丂
丂亙億僀儞僩侾丗晥柺傪妎偊傞亜
偙偺嬋偑嵟戝擄堈搙偱偁傞仛亊俈偵巜掕偝傟偰偄傞桞堦偺棟桼偼丄嬋柤偵偁傞偲偍傝俛俹俵偑俀俆侽偲偄偆嬃堎揑側僥儞億偺懍偝偱偁傞丅俛俹俵俀俆侽丄偡側傢偪婎杮係暘攺偑侾暘娫偵俀俆侽攺偱偁傞偙偲傪堄枴偡傞丅扨弮寁嶼偱丄侾昩娫偵係攺庛丄偡側傢偪侾彫愡嬤偔偑棳傟傞傢偗偱偁傞丅偄偐偵僥儞億偑懍偄嬋偐偳偆偐偍傢偐傝偄偨偩偗傞偱偁傠偆丅偙偺傛偆側嬋傪丄偟偐傕僴僀僗僺乕僪晥柺偱峌棯偡傞偺偼傛偭傐偳桪傟偨斀幩恄宱偑側偄偲柍棟偱偁傠偆丅側偵偟傠丄侾昩偺娫偵俁攺暘偺僆僽僕僃傪扏偐側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅峌棯偺戞侾曕偲偟偰丄傑偢偼晥柺傪妎偊偰偟傑偍偆丅朻摢偱弎傋偨偲偍傝丄僲乕儅儖僗僺乕僪偱僾儗僀偡傞偲傑偭偨偔擄偟偔側偄嬋偱偁傞丅晥柺攝抲偼偐側傝堈偟偔丄弶怱幰偱傕廩暘扏偒偒傟傞偼偢偱偁傞丅僴僀僗僺乕僪偺峌棯偺偨傔偵丄偟偽傜偔偼僲乕儅儖僗僺乕僪偱僾儗僀偟偰丄晥柺傪妎偊偰偟傑偆偙偲丅偝偡偑偵俛俹俵偑崅偄偨傔丄侾嬋偺晥柺偺挿偝偼偐側傝偺傕偺偵側傞偑丄姰帏偵妎偊傞昁梫偼側偄丅晥柺傪妎偊傞偲偄偆傛傝偼丄塣巜朄傪恎偵偮偗傞偙偲偑廳梫側偺偱偁傞丅偦傜偱傕帺慠偵塣巜偱偒傞傑偱偵側偭偰偟傑偊偽丄偙偺嬋偺峌棯偼傎傏偱偒偨偲尵偊傛偆丅
丂亙億僀儞僩俀丗僗僺乕僪偵姷傟傞亜
塣巜偑偁傞掱搙恎偵偮偄偰偒偨傜丄偝偭偦偔僴僀僗僺乕僪偱偙偺嬋傪僾儗僀偟偰傒傛偆丅傑偢嵟弶偺偆偪偼丄偦偺僗僺乕僪偵偮偄偰偄偗偢丄偣偭偐偔恎偵偮偗偨塣巜傕僗儉乕僘偵弌偣側偄偆偪偵廔傢偭偰偟傑偆偩傠偆丅嵟弶偼偙傟偱傕慡慠偐傑傢側偄丅壗搙傕孞傝曉偟僾儗僀傪懕偗傞偆偪偵丄僆僽僕僃僗僋儘乕儖偺僗僺乕僪偵偩傫偩傫姷傟偰偔傞偼偢偱偁傞丅僗僺乕僪偵姷傟偰偔傟偽丄晥柺傕偩傫偩傫尒偊偰偔傞丅壗搙傕偄偆偲偍傝丄偙偺嬋偺嵟戝偺擄揰偼僥儞億偺懍偝丅偁傑傝偵僥儞億偑懍偄屘偵晥柺偑尒偵偔偄偨傔丄億僀儞僩侾偱偼晥柺傪妎偊丄塣巜傪恎偵偮偗偨丅偁偲偼丄偦偺僥儞億偺懍偝傪崕暈偝偊偡傟偽丄偙偺嬋偺峌棯偼娙扨偱偁傞丅偙偺嬋偵尷偭偰偼丄塣巜偺僥僋僯僢僋塢乆傛傝傕斀幩恄宱傗僾儗僀偺僙儞僗側偳偑廳梫側峌棯梫慺偱偁傠偆丅
嵟屻偵丄嬋嵟屻偱搊応偡傞晥柺傪徯夘偡傞丅
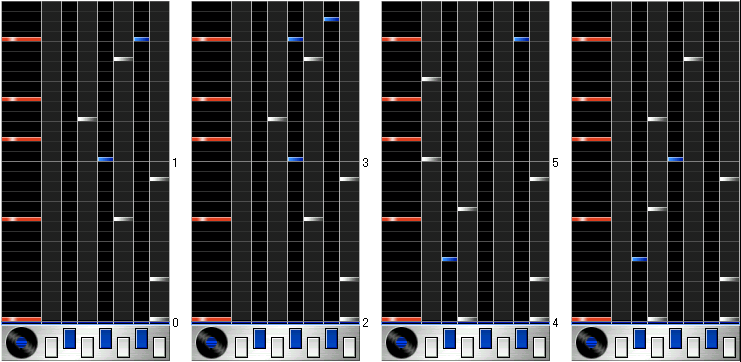
偙偺嬋偺拞偱丄傕偭偲傕擄堈搙偺崅偄晥柺攝抲偲側偭偰偄傞晹暘偱偁傞丅堦斣擄偟偄尞斦偝偽偒偺晹暘偱偝偊丄偙偺掱搙偺攝抲側偺偩丅偄偐偵偙偺嬋偺擄偟偄偲偙傠偑乽僗僺乕僪偩偗乿偱偁傞偐偑傢偐傞偱偁傠偆丅塣巜傪妎偊丄僗僺乕僪偵姷傟偰偟傑偊偽丄僼儖僐儞儃傕壜擻丅偤傂偲傕僼儖僐儞儃傪栚巜偟偰偑傫偽偭偰傎偟偄丅
戞俀俉夞丂尋媶僥乕儅丗kamikaze丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧俀俋擔乮栘乯
傕偲傕偲塀偟嬋偵巜掕偝傟偰偄偨丄媣乆偺dj nagureo偺妝嬋偱偁傞丅偐偮偰丄嘦俢倃2nd偵乽dong-tepo No.1乿偲偄偆崅擄堈搙偺僥僋僲嬋傪採嫙偟偨nagureo巵偱偁傞偑丄偙偺嬋偼dong-tepo傎偳偺嫢埆偝傕側偔丄僥僋僲偺婎杮偵拤幚側偔傝曉偟僼儗乕僘傪懡梡偟偰偄傞丅側偍丄偙偺嬋偺弌尰忦審偼乽仛亊俈偺嬋傪儃乕僟乕偱僋儕傾偡傞乿偙偲偱丄師偺僗僥乕僕偐傜弌尰偲側偭偰偄偨丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仚亜丂
丂亙彉斦亜
傑偭偨偔栤戣偑側偄偱偁傠偆丅傑偩偳偝偭偲僆僽僕僃偺崀偭偰偙側偄彉斦偺偆偪偵丄婎杮僼儗乕僘偺僷僞乕儞傪偮偐傫偱偟傑偍偆丅偙偺晹暘偱搊応偡傞僷僞乕儞偺偔傝曉偟偑丄偙偺嬋偺婎杮偱偁傞丅
丂亙拞斦亜
彮偟栵夘側攝抲偲側偭偰偄傞丄埲壓偺晥柺丅
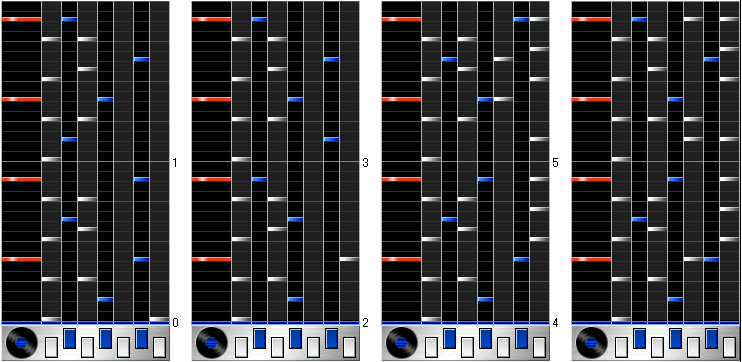
尞斦偩偗偱側偔丄僗僋儔僢僠傕偐傜傫偱偄偰彮偟崬傒崌偭偨晥柺偵側偭偰偄傞丅塣巜偺婎杮偼丄侾乣俁斣傪嵍庤丄係乣俈斣偑塃庤偱偁傞丅昿斏偵搊応偡傞乽侾仺俁仺俀乿偺侾俇暘偼丄曅庤偱僗儉乕僘偵弌偣傞傛偆偵偟偰偍偙偆丅偙偙偺塣巜朄朄偼偄傠偄傠側僷僞乕儞偑峫偊傜傟傞偑丄帺暘偺傗傝傗偡偄塣巜朄傪尒偮偗偩偟偰傎偟偄丅嶲峫傑偱偵丄傗傑偒偺塣巜曽朄偼乽拞巜仺恖嵎偟巜仺拞巜乿偲側偭偰偄傞丅側偍丄俀俹懁僾儗僀偺恖側傜丄俉彫愡栚偺嵟屻偵弌偰偔傞乽俀丒俆丒俈亄俽乿偺晹暘偼乽俀丒俆乿傪嵍庤偱丄乽俈亄俽乿傪塃庤偱庢傞曽偑傗傝傗偡偄偲巚傢傟傞丅
丂亙廔斦亜
拞斦偱搊応偟偨晥柺偑嵞傃搊応偡傞偺偱丄摿偵愢柧偼偄傜側偄偱偁傠偆丅嬋偺嵟屻偼暿僷僞乕儞偺晥柺偲側偭偰偄傞偑丄偙傟傕摿偵擄偟偄尞斦攝抲偱偼側偄偺偱丄晥柺偼妱垽偡傞丅側偍丄嬋慡懱傪捠偟偰彮偟敾掕偑尩偟傔偵姶偠傜傟傞丅婎杮儕僘儉偑偼偭偒傝偟偰偄傞嬋側偺偱丄僗僐傾傾僞僢僋傪栚巜偡恖偼僥儞億偲儕僘儉傪偟偭偐傝偮偐傫偱椪傫偱傎偟偄丅摿偵曅庤偱偝偽偔侾俇暘偺晹暘偼丄戝偞偭傁偵棳偝側偄偱儕僘儉捠傝偵扏偔傛偆偵怱偑偗傞偙偲丅侾俀俆侽乣侾俁侽侽揰庢傟傟偽丄偐側傝惓妋偵扏偗偰偄傞偲巚傢傟傞丅
戞俀俈夞丂尋媶僥乕儅丗LUV TO ME乣UCCHIE'S EDITION乣丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧俀係擔乮搚乯
傑偩俈尞斦僞僀僾偺嘦俢倃偑搊応偡傞埲慜丄beatmania 3rd mix偵偰弶搊応偟偰戝僸僢僩傪屇傫偩儐乕儘價乕僩乽LUV TO ME乿偺傾儗儞僕僶乕僕儑儞丅側偵偘偵disco mix偲偄偆暿傾儗儞僕僶乕僕儑儞傕懚嵼偡傞偺偩偑丄偳偪傜傕嘦俢倃偱妝偟傓偙偲偑偱偒傞丅側偍丄尨嬋偺曽偼丄beatmania嘨偵偰妝偟傓偙偲偑偱偒傞丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛亜丂
丂亙彉斦亜
偝偰偙偺嬋丄偗偭偙偆偄偨傞偲偙傠偱侾俇楢僔儞僙僞儉偑搊応偡傞偑丄敾掕偑傗傗尩偟偄偺偱柍惛傪偣偢椉庤偱偟偭偐傝僞僀儈儞僌傪寁傝側偑傜扏偄偨曽偑偄偄偐傕偟傟側偄丅僞僀儈儞僌揑偵偼丄傗傗憗傔偵扏偔偲GREAT偑弌傗偡偄傛偆偱偁傞丅懠偵摿暿尩偟偄晥柺傕搊応偟側偄偺偱丄愢柧偼埲忋丅
丂亙拞斦亜
僒價偵偝偟偐偐傞晹暘丅僗僋儔僢僠傕抐懕揑偵偐傜傫偱偒偰丄偙偺嬋嵟戝偺嶳応傪寎偊傞偑丄偦偺拞偱埲壓偺晥柺丅
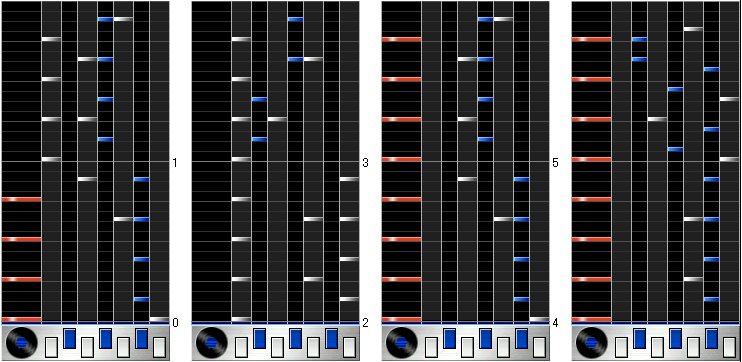
侾乣係彫愡栚偵偮偄偰偼摿偵壗傕尵偆偙偲偼側偄偱偁傠偆丅俆乣俉彫愡栚偵偮偄偰丄摿偵嵟屻偺俉彫愡栚側偳偼丄弶怱幰偑戝偒偔僎乕僕傪尭傜偡偲偙傠偐傕偟傟側偄丅椻惷偵側偭偰晥柺傪尒偰傒傞偲丄僗僋儔僢僠偺僞僀儈儞僌傕婎杮攺偱堦掕偟偰偄傞偟丄尞斦攝抲偵傕擄偁傝偲尵偆傎偳偺傕偺偱偼側偄偑丄幚嵺偵扏偔偲側傞偲堦嬝撽偱偼偄偐側偄偲偄偆偺偑幚忣偐傕抦傟側偄丅偙偺応柺偺堦斣偺峌棯朄偼丄曅庤偱尞斦憖嶌偑偱偒傞傛偆偵側傞偙偲偱偁傞丅忋偱傕弎傋偨偲偍傝丄寛偟偰尞斦攝抲偩偗偲偭偰傒傟偽擄偟偄傢偗偱偼側偄偺偱丄廩暘曅庤偱偙側偣傞丅尞斦傪曅庤偱憖嶌偱偒傞傛偆偵側傟偽丄傕偆曅曽偺庤偼姰慡偵僼儕乕偵側傞偺偱丄僗僋儔僢僠偺傒偵愱擮偱偒傞偲偄偆傢偗偩丅俉彫愡栚偺尞斦攝抲偼婎杮攺柍帇偺侾俇暘僞儉懪偪側偺偩偑丄偙偙傕偱偒傟偽曅庤偱僗儉乕僘偵庢傟傞傛偆偵丅
丂亙廔斦亜
彉斦偲傎傏摨偠晥柺攝抲丅偙偙傑偱棃傟偽傎傏埨怱偱偁傠偆丅拞斦嵟屻偱戝偒偔僎乕僕傪尭傜偟偰偄側偄尷傝僋儕傾偼埨懽偱偁傞偑丄偙偺嬋偵偼偍傑偗乮嬋偑廔傢偭偨偲尒偣偐偗偰丄嵟屻偺嵟屻偵僆僽僕僃偑怳偭偰偔傞偙偲乯偑偁傞偺偱丄嵟屻傑偱婥傪敳偐側偄傛偆偵丅偙偺偍傑偗傪庢傝懝偹偰僋儕傾傪摝偡側偳偲偄偆偺偼嬸偺崪捀偱偁傞丅
戞俀俇夞丂尋媶僥乕儅丗Voltage丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧俀侾擔乮悈乯
僪儔儉壒偑拞怱偺價僢僌價乕僩丅弶傔偰僾儗僀偡傞恖偺搙娞傪敳偔乽巭傑傞僆僽僕僃乿偺墘弌偑巃怴偩偑丄偦傟埲奜偵傕嵟屻偺僆僽僕僃儔僢僔儏側偳偵傕偐側傝庤傪從偔偺偱偼側偐傠偆偐丅彉斦偼乽巭傑傞僆僽僕僃乿偺偨傔偵俛俹俵偑寖偟偔曄壔偟丄曄懃揑側僥儞億傪崗傓偑丄嬋屻敿偐傜偼惓懃偺4/4攺巕偲側傞丅慡懱傪捠偟偰偲偄偆傛傝偼丄埲壓偱徯夘偡傞俀応柺偑僋儕傾偵戝偒偔娭學偡傞晥柺偲側偭偰偄傞丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仚亜丂
丂亙彉斦亜
偙偺嬋偺戝偒側摿挜偲側偭偰偄傞丄乽巭傑傞僆僽僕僃乿偺晹暘偺晥柺丅
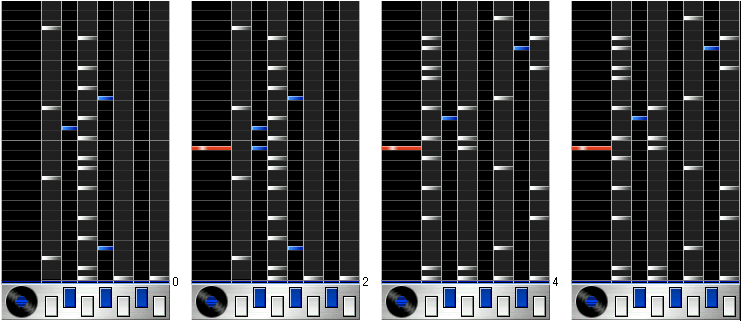
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
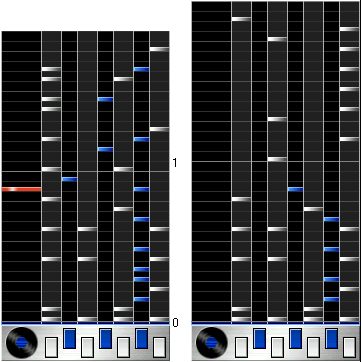
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
丂
巭傑傞偺偼丄婏悢斣栚偺彫愡偺侾攺栚偱偁傞丅幚嵺偼姰慡偵巭傑傞偺偱偼側偔偰丄偛偔備偭偔傝偲僆僽僕僃偼摦偄偰偄傞丅偐偲偄偭偰丄栚墴偟偱偼僞僀儈儞僌傪堩偟傗偡偔丄俛俹俵偑尦偵栠偭偰偐傜偺僼僅儘乕傕抶傟偑偪偵側傞偺偱丄僞僀儈儞僌傪偟偭偐傝攃埇偟傛偆丅俛俹俵偼僆僽僕僃偑巭傑傞弖娫偵尦偺1/4偵側傞偺偱丄晥柺偱偼侾俇暘娫妘偺僆僽僕僃攝抲偲側偭偰偄傞偑丄幚嵺偵偼係暘娫妘偱扏偔偙偲偵側傞丅傑偨丄俛俹俵偑堦婥偵棊偪傞偺偱丄俀攺栚偺尞斦偼傛偔堷偒偮偗偰偐傜扏偔傛偆偵丅憗偔扏偒偡偓傞偲俛俙俢偵側傞丅
丂亙拞斦亜
摿偵尩偟偄攝抲偑搊応偡傞応柺偼側偄偟丄俛俹俵傕僥儞億傕惓懃偵栠傞偺偱丄壗傕栤戣偑側偄丅偙偙偱偟偭偐傝僎乕僕傪挋傔偰偍偔傛偆偵偟偨偄丅
丂亙廔斦亜
僆僽僕僃儔僢僔儏偲側傞丄堦斣嵟屻偺応柺偺晥柺丅
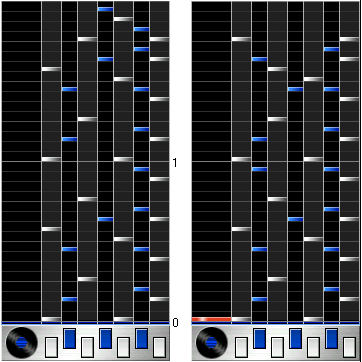
俆乣俈斣偑偐側傝婯懃揑側尞斦攝抲偵側偭偰偄傞丅偙偙偑儈僜丅偮偄偱偵偄偊偽丄侾乣係斣偺攝抲傕婯懃惈偑尒傜傟傞丅嵍庤偱侾乣係斣丄塃庤偱俆乣俈斣傪扴摉偡傞偺偑傛偄丅俀彫愡栚偺嵟屻乣俁彫愡栚傾僞儅偵偐偗偰偺乽俈仺俇仺俈仺俇仺俆仺係仺俆乿偺奒抜晥柺偼丄俀俹懁僾儗僀儎乕偵偼彮偟朲偟偄晥柺偐傕偟傟側偄偑丄奒抜墴偟偱庢傞傛傝傕乽俆仺係仺俆乿傪岎屳墴偟偱墴偡曽偑僾儗僀偟傗偡偄丅偙偺帪丄俁彫愡栚傾僞儅偺侾斣偺僼僅儘乕偑抶傟側偄傛偆偵丅偙偺奒抜晹暘偵尷傝丄係斣傪柍帇偡傞曽朄傕峫偊傜傟傞丅
戞俀俆夞丂尋媶僥乕儅丗minimalian丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧侾俋擔乮寧乯
傕偲傕偲塀偟嬋偵側偭偰偄偨偑丄崱偱偼夝嬛偝傟偰STAGE俀偐傜慖嬋偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞丅偙偺嬋偺弌尰忦審偼偄傑偄偪傗傑偒偵傕傢偐傜側偐偭偨偺偩偑丄桳椡愢偲偟偰偼堦掕悢埲忋偺僐儞儃傪払惉偡傞偙偲偱弌尰丅堦晹偱偼仛亊俇偺嬋傪僋儕傾偡傞偲弌尰偡傞偲僂儚僒偝傟偰偄偨偑丄仛亊俇偺嬋偼STAGE侾偱慖嬋偱偒側偄偺偵懳偟偰丄夝嬛屻偼STAGE俀偐傜弌尰偡傞偙偲偐傜丄偙偺忦審偱偼側偄偲巚傢傟傞丅傫傑偀丄崱偲側偭偰偼偳偆偱傕偄偄傫偩偗偳偹乧丅丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仛亜丂
丂亙彉斦亜
弶傔偺偆偪偱彮偟栵夘偲巚傢傟傞偺偑埲壓偺晥柺丅
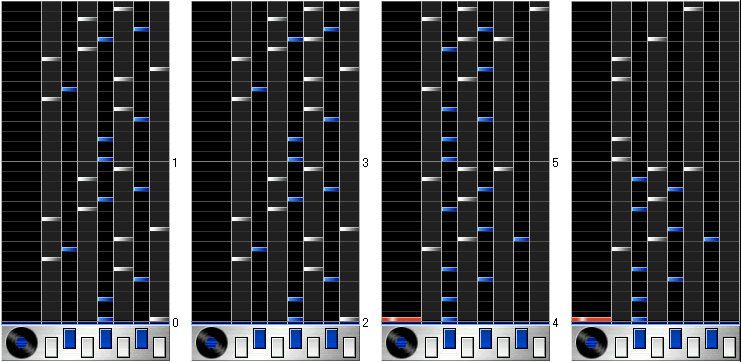
尞斦偑偐側傝暋嶨偵棈傒崌偭偰偄傞偙偺晹暘丄幚嵺偵僾儗僀偟偰傒傞偲側偐側偐攝抲傪尒嬌傔傞偺偼崲擄偐傕偟傟側偄丅偙偆偄偆晥柺偺峌棯偵偼丄壗搙傕僾儗僀偟偰晥柺傪妎偊傞偙偲偑堦斣廳梫側偺偩偑丄偦傟埲慜偵婎杮揑側偙偲偲偟偰丄儈僯儅儖宯偺妝嬋偼摨偠攝抲偺嵶偐偄偔傝曉偟偑婎杮偵側偭偰偄傞偙偲傪墴偝偊偰偍偙偆丅偙傟傪抦偭偰偄傞偩偗偱丄堄奜偲峌棯偺庤彆偗偵側偭偨傝偡傞傕偺偱偁傞丅
丂亙拞斦亜
偦傟傎偳栵夘側晥柺偼弌偰偙側偄丅嬋慡懱傪捠偟偰丄俉彫愡偛偲偵僼儗乕僘偑曄壔偟偰偄偔偺偱丄嬋挷傗僼儗乕僘偺曄壔傪偟偭偐傝墴偝偊偰偄偔偲娙扨偵峌棯偱偒傞偙偲偲巚偆丅
丂亙廔斦亜
嵟屻偺俉彫愡偺晥柺傪埲壓偵徯夘偟傛偆丅
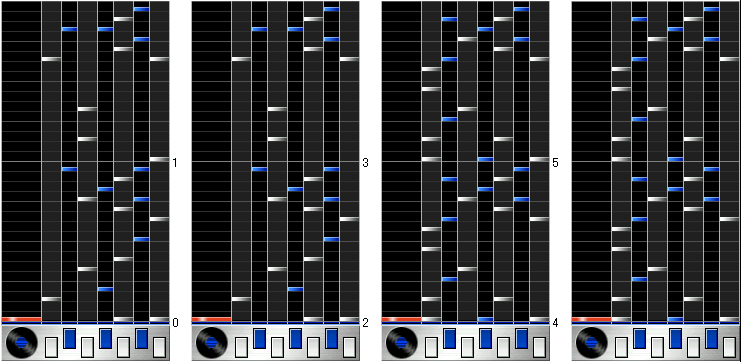
奺彫愡偺屻敿偵搊応偡傞奒抜晥柺偑偐側傝栵夘丅摿偵拲堄偡傋偒側偺偼丄係彫愡栚偲俆彫愡栚偺偮側偓偺晹暘丅偙偙偱戝偒偔僎乕僕傪尭傜偟偰偟傑偆偲丄偁偲偺晥柺偱傛偭傐偳惈奿偵扏偐側偄偲僋儕傾偑婋偆偄丅偨偩丄岾偄側偙偲偵塣巜曽朄偼俉彫愡傪捠偠偰摨偠偱偁傞丅庡偲側傞奒抜晥柺偺乽俈仺俆仺俇仺係仺俆仺俇乿傪塃庤偱丄暃偺乽俁仺俀乿傪嵍庤偱僇僶乕偡傞塣巜偱俷俲丅慜敿係彫愡偺暃塣巜偲屻敿係彫愡偺暃塣巜偲偱偼僞僀儈儞僌偑堘偆揰偵拲堄丅姷傟偰偔傟偽丄慡晹偺尞斦傪偟偭偐傝庢傝偒傟傞偼偢丅弶傔偺偆偪偼柍帇偡傞僆僽僕僃偑偁偭偰傕偄偄偑丄嵟廔揑偵偼慡晹庢傟傞傛偆偵側傠偆丅傕偭偲傕丄偳偙傪柍帇偡傞偐偺敾抐傕僋儕傾偵娭傢偭偰偔傞偺偩偑乧丅傑偨俀俹懁僾儗僀偺恖偼丄奒抜晥柺傪塃庤偱庢偭偨捈屻偵僉乕仌僗僋儔僢僠傪懄嵗偵弌偣傞傛偆偵楙廗偡傞昁梫偁傝丅
戞俀係夞丂尋媶僥乕儅丗CHECKING YOU OUT丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧侾俇擔乮嬥乯
beatmania巎忋丄傕偭偲傕擄搙偺崅偄僸僢僾儂僢僾偱偼側偄偩傠偆偐丅嬋偺搑拞偱俛俹俵偑曄壔偡傞偲偙傠傕偝傞偙偲側偑傜丄奺強偵搊応偡傞俁楢晞僗僋儔僢僠偑偐側傝偺嬋幰丅崬傒崌偭偨僗僋儔僢僠晥柺偵側傞偲弶怱幰傎偳僞乕儞僥乕僽儖傪埮塤偵夞偟偑偪偩偑丄偙偺嬋偼僗僋儔僢僠拞怱側偺偱丄夞偟偡偓偵偼廫暘拲堄偑昁梫偱偁傞丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仛仚亜丂
丂亙彉斦乣拞斦亜
偺偭偗偐傜偽傫偽傫僗僋儔僢僠晥柺偑搊応偡傞丅俛俹俵偑娚傗偐側彉斦偺偆偪偵丄僗僋儔僢僠傪偲傞僞僀儈儞僌傪偮偐傫偱偟傑偆偙偲偑旕忢偵廳梫丅傕偲傕偲偺僥儞億偼傑偭偨偔懍偄傕偺偱偼側偄偺偱丄傗傗崬傒崌偭偨晥柺偵尒偊偰偟傑偆偑丄拲堄偟偰晥柺傪尒偰偄傞偲丄楢僗僋儔僢僠晥柺偱傕乽侾俇暘崗傒乿偲乽俇楢晞崗傒乿偺俀庬椶偑偁傞偙偲偵婥偯偔偐偲巚偆丅傑偨丄楢僗僋儔僢僠晹暘偱偼丄僞乕儞僥乕僽儖傪偟偭偐傝慜屻偵夞偝側偄偲僞乕儞僥乕僽儖偑斀墳偣偢丄巚傢偸儈僗偺楢敪傪屇傇偙偲偵側傞丅側偍丄偙傟偼嬋慡懱傪捠偟偰尵偊傞偙偲偩偑丄尞斦攝抲偵偼傑偭偨偔擄搙偺崅偄応柺偑懚嵼偟側偄丅傗偼傝僗僋儔僢僠偺庢傝曽偑傕偺傪偄偆嬋偱偁傠偆丅
丂亙廔斦亜
廔斦偵擖傞偲丄俛俹俵偑偄偒側傝攞偵挼偹忋偑傞丅偦偺晹暘偺晥柺傪慡晹徯夘偟偰傒傛偆丅
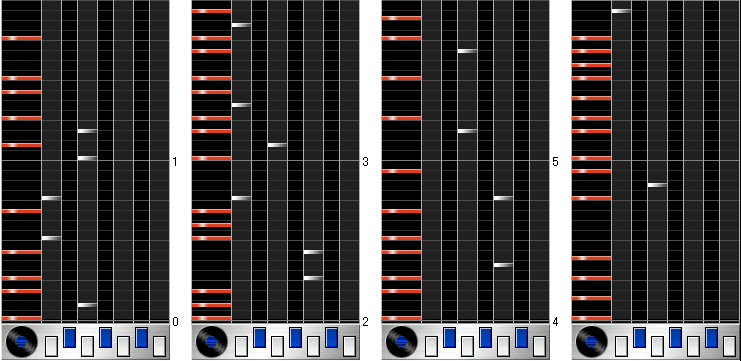
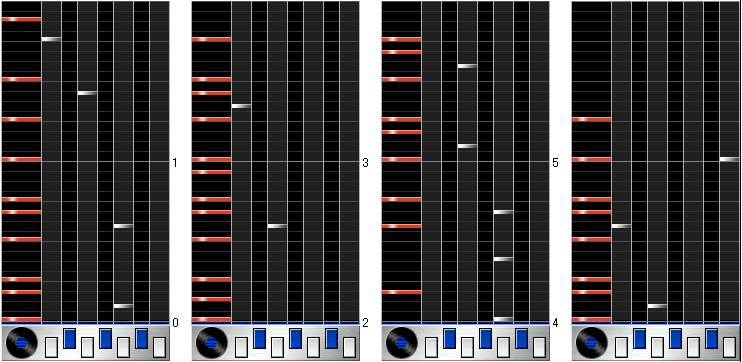
偙偺捠傝丄晥柺偺傎偲傫偳偑僗僋儔僢僠偱愯傔傜傟偰偄傞丅偙偺応柺偺栵夘側偲偙傠偼丄晥柺偺棊壓懍搙偑恞忢偠傖側偔懍偄忋偵崬傒崌偭偨晥柺偵側偭偰偄傞偨傔丄嬻懪偪偑嫋偝傟側偄偲偙傠偱偁傞丅崬傒崌偭偨応柺偱堦搙嬻懪偪傪弌偟偰偟傑偭偨偑嵟屻丄堦楢偺晥柺儔僢僔儏偱俛俙俢楢敪偲側傝丄戝偒側幐揰傪彽偔丅偙偺応柺偺僗僋儔僢僠偺婎杮僞僀儈儞僌偼乽俁楢晞崗傒偺拞敳偒乿丅偦偺僞僀儈儞僌偼晥柺棊壓懍搙偑曄傢偭偰傕彉斦偺僞僀儈儞僌偲曄傢傜側偄丅棊偪拝偄偰僆僽僕僃傪傛偔尒側偑傜僞乕儞僥乕僽儖傪夞偦偆丅偳偆偟偰傕僆僽僕僃偵懳偟偰僞乕儞僥乕僽儖傪憗偔夞偦偆偲偟偑偪偩偑丄偙傟偼嬻懪偪傪彽偔梫場偵側傞偺偱丄傓偟傠偙偺応柺偼婥帩偪抶傔偵僗僋儔僢僠傪慱偭偨曽偑偄偄偐傕偟傟側偄丅偦傟偐傜嵶偐偄偙偲偩偑丄偙偙偵傕旝柇側偲偙傠偱乽俉暘崗傒乿僞僀儈儞僌偺僗僋儔僢僠晥柺偑懚嵼偡傞丅忋偱傕弎傋偨偲偍傝丄偙偙偱偼嬻懪偪偵偼尩廳拲堄丅俉暘崗傒偺晹暘傪俁楢晞偺僞僀儈儞僌偱夞偟偰偟傑偆偲娫堘偄側偔嬻懪偪偵側傞偺偱丄傛偔晥柺傪尒傞傛偆偵丅側偍丄僋儕傾偺栚埨偲偟偰偼丄偙偺崅懍棊壓抧懷傪敳偗偨帪揰偱丄僎乕僕偑俈侽亾傕巆偭偰偄傟偽傎傏僋儕傾妋掕丅偨偩偟丄偙偺晹暘傪敳偗偨捈屻偵俛俹俵偑尦偺俛俹俵傑偱棊偪傞偺偱丄俛俹俵偺曄壔偵榝傢偝傟偢偵偟偭偐傝尞斦傪庢傞偙偲丅嵟屻偺嵟屻傕尞斦攝抲偵傑偭偨偔擄偟偄偲偙傠偼側偄丅
戞俀俁夞丂尋媶僥乕儅丗empathy丂峌棯丂俀侽侽侾擭俁寧侾係擔乮悈乯
傗傑偒丄僀僠墴偟偺僪儔儉儞儀乕僗丅仛亊俈偺妝嬋偲偟偰偼懡彮暔懌傝側偄偐傕偟傟側偄偑丄偦偺暘弶怱丒拞媺幰偵偲偭偰偼偍庤崰側嬋偱偁傞丅搑拞偱俛俹俵偑曄壔偡傞晹暘傕偁傞偑丄摿偵僋儕傾偵巟忈偑弌傞偙偲偼側偄丅側偍丄俴俬俧俫俿俈儌乕僪偩偲僆僽僕僃棊壓懍搙偼曄傢傜側偄偑丄俈俲俤倄俽儌乕僪偩偲俛俹俵偺曄壔偵敽偭偰僆僽僕僃棊壓懍搙偑曄壔偡傞丅
亙傗傑偒揑妝嬋擄堈搙昡壙丗仛仛仛仛仛仚亜丂
丂亙彉斦亜
拞斦偵偝偟偐偐傞傑偱偺丄埲壓偺傛偆側僆僽僕僃儔僢僔儏丅
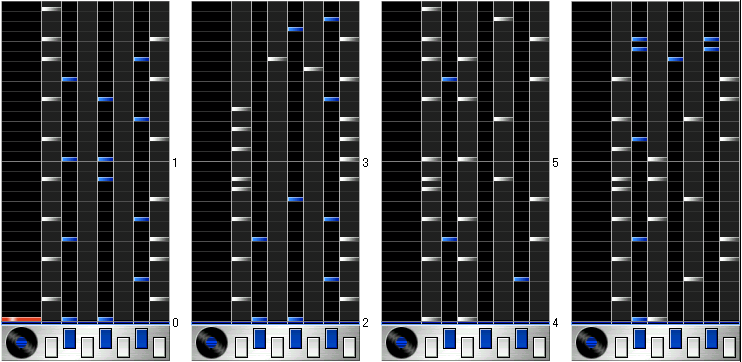
俛俹俵偑傗傗崅偄嬋側偺偱丄嵟弶偺偆偪偼偮偄偰偄偒偯傜偄晹暘偐傕偟傟側偄丅傑偨丄偙偺晥柺偺捈屻偵俛俹俵偑敿暘偵棊偪傞偨傔丄偦偙偱堷偭偐偐傜側偄傛偆偵丅
丂亙拞斦亜
俛俹俵偑尦偵栠偭偰丄偟偽傜偔屻偵搊応偡傞埲壓偺晥柺丅
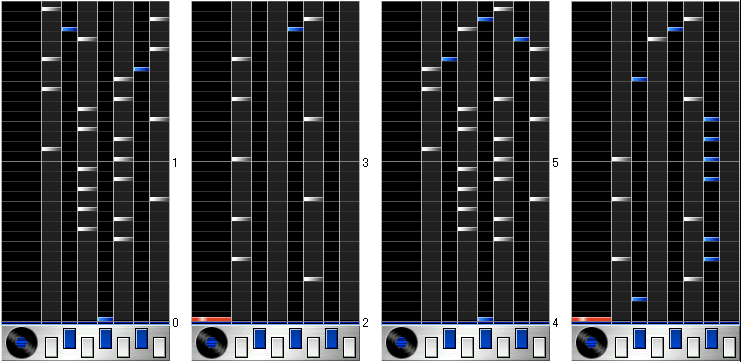
弶怱幰傎偳丄偙偆偄偆晥柺偑弌偰偔傞偲揔摉偵嵍塃偺岎屳懪偪偱偡傝敳偗傜傟傞偩傠偆偲僞僇傪偔偔偭偰丄傔偪傖偔偪傖偵扏偄偰偟傑偄偑偪側偺偩偑丄偙偙偼偦傟傎偳扨弮偱偼側偄傛偆偩丅傑偢偼晥柺傪尋媶偟偰丄扏偒曽傪尋媶偟偰傒傛偆丅偍傑偗偺傛偆偵偔偭偮偄偰偄傞惵尞斦偑丄扨弮側嵍塃偺岎屳懪偪傪岻柇偵朩偘偰偄傞偺偑傢偐傞偱偁傠偆丅
丂亙廔斦亜
忋偺晥柺偺捈屻偵弌偰偔傞丄埲壓偺晥柺丅
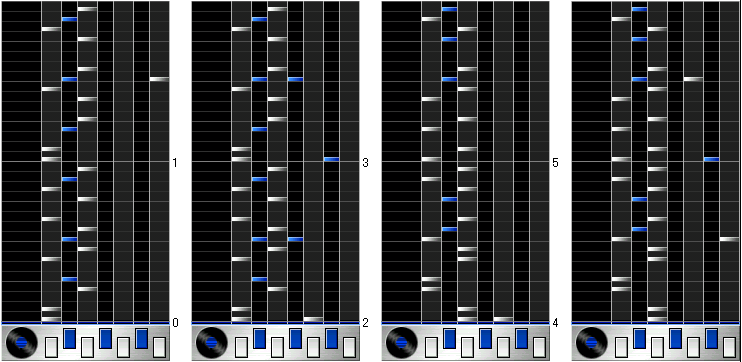
侾乣俁斣傑偱偺攝抲偵拲栚丅侾丒俀彫愡栚偲俁丒係彫愡栚丄摨偠偔俆丒俇彫愡栚偲俈丒俉彫愡栚偼傑偭偨偔摨偠僆僽僕僃攝抲偵側偭偰偄傞偺偑傢偐傞丅偙偙傪傑偢丄娞偲偟偰墴偝偊偰偄偨偩偒偨偄丅偙偙偱弶怱幰偺偨傔偵傇偭偪傖偗偨榖傪偝偣偰傕傜偊偽丄偙偺晹暘偵娭偟偰偼係乣俈斣偺尞斦傪慡偰柍帇偟偰傕廩暘僋儕傾偼慱偊傞丅偟偨偑偭偰丄侾乣俁斣偺儔僢僔儏傪僉儗僀偵扏偗傞傛偆偵側偭偰偝偊偄傟偽丄偙偺嬋偼傎傏僋儕傾偟偨傕摨慠偲尵偊傞丅僋儕傾偺忦審偼丄偙偺屻偵搊応偡傞晥柺傪慡偰庢傟傞傕偺偲壖掕偟偰丄偙偺晹暘傪敳偗偨帪揰偱僎乕僕偑俆侽乣俇侽亾巆偭偰偄傟偽傛偄丅傓傠傫丄拞媺幰埲忋偺曽偼丄偙偺晹暘偼廩暘僼儖僐儞儃傪慱偭偰偄偗傞晥柺側偺偱丄偦傟傪栚昗偵偟偰偄偨偩偒偨偄丅