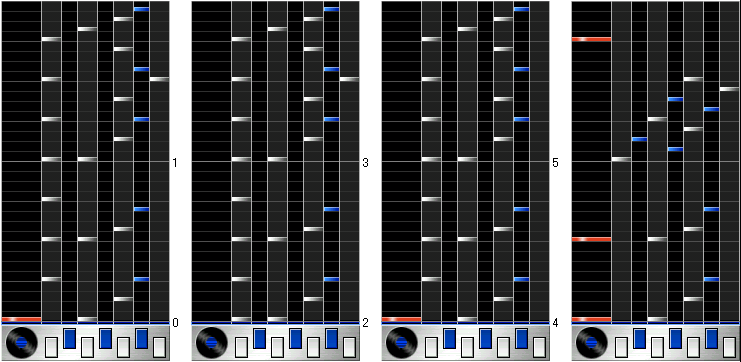
��Q�P��@�����e�[�}�FJIVE INTO THE NIGHT�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���X���i���j
4th style�ɂĐV���Ɏ��^���ꂽ�AD.E.�V���[�Y����̈ڐA�B���Ȃ͂�܂������������Ƃ��Ȃ��̂����A��̑O�ɗ��s�����Ȃł���炵���B���~�U�Ƃ��Ă͓�Փx����⍂���C�����邪�A�v���C���Ă��Ĕ��ɂ������낢���ʔz�u�ɂȂ��Ă��āA���������l�C������Ȃł͂Ȃ����낤���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F��������������
�@�����Ձ�
�C���g�����������Ƃ́A�ȉ��̕��ʁB
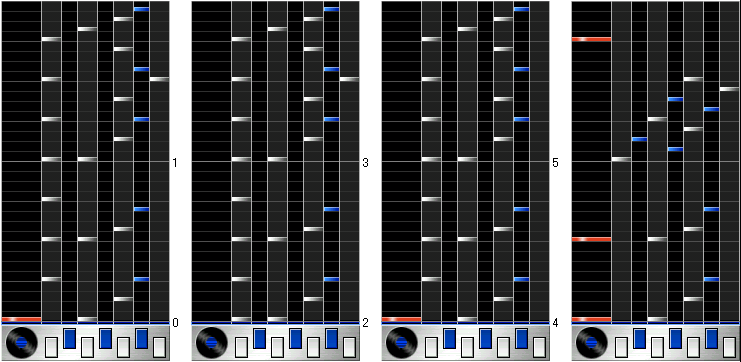
�@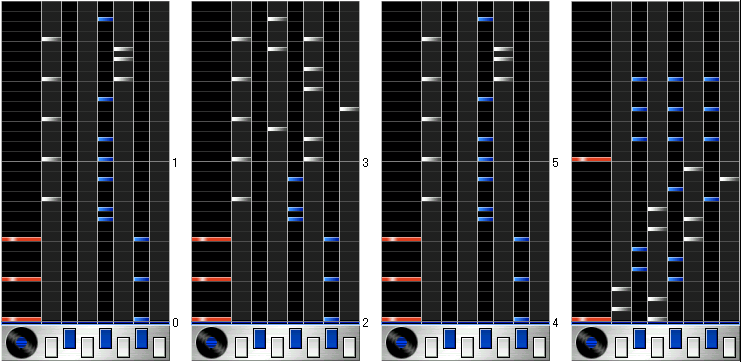
��i���ʁE���i���ʋ��ɁA���̐�����x���o�ꂷ��t���[�Y�ł���B��i���ʂɊւ��ẮA�P�Ԃ����Y���łQ�`�V�Ԃ������f�B�p�[�g�ɂȂ��Ă���B�P�Ԃ�����ŁA����ȊO�̌��Ղ��E��Ŏ��B���Y���͒P���Ȋ�{�S���Ȃ̂ŁA���E�̓����̈Ⴂ�ɂ��邱�Ƃ����܂�Ȃ��Ǝv���B���i���ʂɂ��āA�u�U�{�r�v�́A�Q�o���v���C���[�Ȃ�L�[���X�N���b�`�����p����Ζ������Ȃ���ɐi�߂�B�Q�E�S�E�U���ߖڂ́A��i���ʂƓ��l�P�ԈȊO���E��Ŏ��^�w�Ŗ��Ȃ��B�V���ߖڂɂ��ẮA�K�i�P�U�A�I�u�W�F��Ў�Ŏ��̂����A�P�R���ڈȍ~�́u�S���U���T���V�v�̉^�w�́A�Ў�ł��Ȃ��Â炢�Ƃ����l�͗���̌��݉����ɃX�C�b�`�ł���B���̎��A�W���ߖڂ̓����ɓo�ꂷ��X�N���b�`���x��Ȃ��悤�ɒ��ӁB
�@�����Ձ�
���S�҂̕������̋ȂɃ`�������W�����Ƃ��A�傫���Q�[�W�����炵�₷���ȉ��̕��ʁB
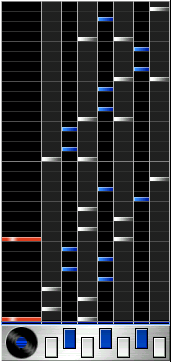
�Ȏ��̂̃X�s�[�h���������A�ˑR�o�Ă���ꂽ��ǂ������������Ƃ܂ǂ����ʂł��邩������Ȃ����A�P���ߖڂ̊K�i�P�U�A�͏��Ղ̍��Ő��������Ƃ���ɂ��Ȃ��Ƃ��āA�Q���ߖڂ́u�����Ղ�����ŁA���Ղ��E��Łv���悤�ɗ��K���Ă݂�B���Ȃ݂ɂ�܂��̏ꍇ�́A�ȉ��̉^�w�B�i��������A���F���E��j
�P�E�R���Q���Q���R�E�T���S���S���T�E�V���U���U���R�E�T���S���V
�@���I�Ձ�
�Ō�ɓo�ꂷ��A�ȉ��̕��ʁB
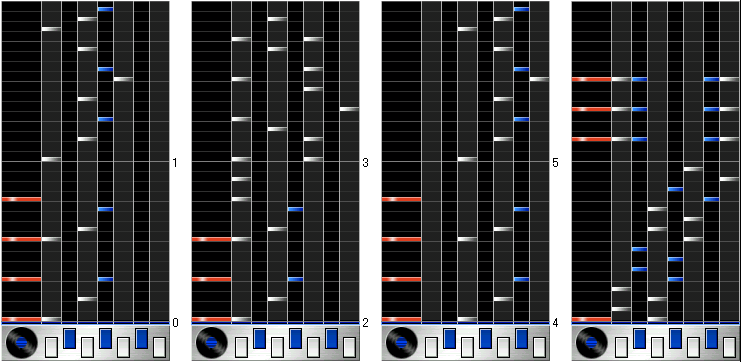
�����f�B�p�[�g�ɃX�N���b�`���f���I�ɂ����ł��āA���Ȃ���ȕ��ʁB�P�E�R�E�T���ߖڂ͌��Ղ�Ў�ł��Ȃ���悤�ɂȂ�Ί����B�Q�E�S�E�U���ߖڂ͌��Ղ����Ȃ̂ŗ���ł��Ȃ��B�V���ߖڂ͂��Ȃ��݂̊K�i�P�U�A�I�u�W�F�Ȃ̂Ő����͂���Ȃ��ł��낤�B�W���ߖڂ́u�P�E�Q�E�U�E�V�{�r�v�̓��������́A�P�o���v���C�Ȃ�u�P�E�Q�{�r�v�A�Q�o���v���C�Ȃ�u�U�E�V�{�r�v�̃L�[���X�N���b�`���ł���悤�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ɛh���B�L�[���X�N���b�`�̃R�c�́A����i�Q�o���v���C�Ȃ�E�肾���j�̏��w�̕����Ń^�[���e�[�u����������悤�ɉ��ƁB�Ȃ�ׂ���͍L�����܂��āA������̓����傫�����Ȃ��ƃ^�[���e�[�u�����������Ȃ��B���̋Z�p�͉���Ă����ƂقƂ�ǂ̋Ȃŏd��i�Ƃ������A����Փx�̋ȂɂȂ�Ƃ��̋Z���g��Ȃ��ƃN���A���ł��Ȃ��c�j�B������@�ɁA���ЂƂ��}�X�^�[���Ă��������B
��Q�O��@�����e�[�}�FBroken My Heart�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���W���i�j
�uCAN'T STOP FALLIN' IN LOVE�v�ɑ����ANAOKI�̃n�C�p�[���[���r�[�g��Q�e�B�uCAN'T STOP�c�v�Ɣ�ׂ�ƁA�����̔߂����ȕ��͋C���������o���Ă��邱�̋ȁA���͉̎��I�ɂ��uCAN'T STOP�c�v�̐��E����Ȃ����Ă���炵���ł��B�����āA���̑����́cDDR�ł����Ȃ��݂́uLOVE AGAIN TONIGHT�v�ɂȂ����Ă��邻���ł��B����������В����Ă݂����ł��ˁB
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�������`A�����`B������
�������͑S�����Ȃ��BA�����̕����́A�P�E�R�Ԃ𒆐S�Ƃ������Y���p�[�g�����C���B��������܂��傫�Ȗ��͂Ȃ��BB�����ł͌��Օ��ʂɃX�N���b�`�������ł��ď����Z�������ʂɂȂ��Ă���B�����ł͕��ʂ͊��������Ă����������A���ɓ�x�̍����^�w��K�v�Ƃ��镔���ł��Ȃ��̂ł����������Ɣ����Ă������������B
�@���T�r��
�T�r�͂���ɑ���C�����EB�����̌�ɍĂь��Քz�u���ς�����`�œo�ꂷ��B�܂��͊�{�ƂȂ�A�n�߂ɓo�ꂷ��T�r�̕��ʂ��Љ�悤�B
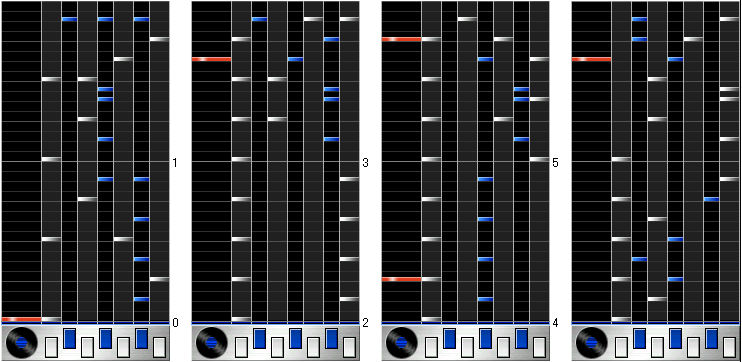
�������ɓo�ꂷ��T�r���ʂ́A��̕��ʂ������Ƃ����Ⴒ����Ƃ��ĖZ�������ʂɂȂ��Ă���̂ŁA��{����������Ƃ����Ӗ��ł������Љ���B�������������艟����悤�ɂȂ���̂��Ƃ̍U���������Ɨe�ՂɂȂ邱�Ƃł��낤�B���̕��������Ɋւ��Č����A��͂���ɓ�����ʂł͂Ȃ��B
�@��C������
��̕��ʂ̒���ɓo�ꂷ��A�ȉ��̂悤�ȊK�i���ʒ��S�̕����ł���B
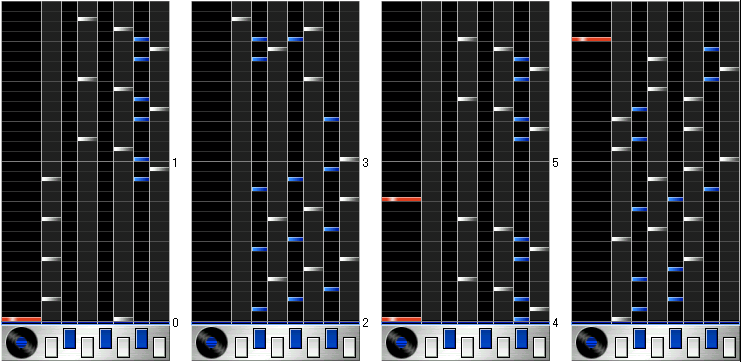
�P�o���v���C�Ȃ����قǓ���Ȃ��N���A�ł��镔�������A�Q�o���v���C���[�ɂ́A�T���ߖڂɓo�ꂷ��u�U���V���U���T���R�v�̊K�i�ƃX�N���b�`���Ɏ���ʂŁA����ŊK�i���ʂ����Ƃ��Ɏ��s���₷����������Ȃ��B�E��ō����̕��ʂ����͖̂�肪�Ȃ��̂����A����ʼnE���̕��ʂ����̂́A���ɉE�����̐l�͌��Պ��o�����ɓ����Ă��Ȃ��ƃX�J���₷���̂ŁA�����������ӁB
�@������ȍ~��
����C�����ȍ~�́A�Ă�B��������T�r�ɂȂ���p�^�[���B��ԃ��X�g�ɓo�ꂷ��A������Ƃ����I�u�W�F���b�V���̕����͂Q�o���v���C�̐l���悭���s���Ă���̂���������B���ʂ͊��������Ă����������A���������ĕ��ʂ�����Ό����Ē@���Ȃ��z�u�ł͂Ȃ��A�Ƃ������A�S�����̂Ȃ����ʂł���B�Ō�܂ŋC�����ɂ�����L���Ă������������B
��P�X��@�����e�[�}�FFANTASY�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���V���i���j
���Ȃ�EARTH WIND&FIRE�̒����ȁBD.E.�o�[�W�����Ƃ������Ƃła�o�l�����Ȃ荂���A���I�u�W�F�����X�O�O�ȏ�Ƃ��Ȃ蒷�����ʂɂȂ��Ă��邪�A�X�O�O�ȏ�̃I�u�W�F��������^�Ȃ̒��ł͈�ԊȒP�ŁA�_�������₷���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
�܂��̓I�[�v�j���O�̕��ʁB

�P�o���v���C���[�Ȃ�A�ŏ��́u�P�E�S�E�U�{�r�v�͊ȒP�Ɏ���B�Q�o���v���C���[�̏ꍇ�́A���ՑS�Ă�����Ŏ��^�w�p�^�[���ƁA�u�P�{�S�v������A�u�U�{�r�v���E��Ŏ��^�w�p�^�[�����l������B�Ȃ��A�X���ߖڂɂłĂ���K�i���ʂ́A�P�E�R�Ԃ�����ŁA�u�T���U���V�v���E��ŁB�I�u�W�F�̗������x�̑����ɂƂ܂ǂ���������Ȃ����A���ӎ��ɉ^�w�ł���悤�C���[�W�g���[�j���O���Ă����Ƃ悢��������Ȃ��B
�܂��A���Ղ̍Ō�ɂłĂ���ȉ��̕��ʁB
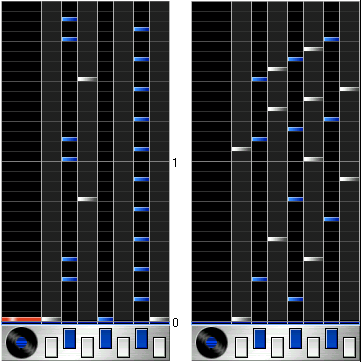
�u�P�E�S�E�V�{�r�v�̔z�u���A���S�҂ɂƂ��Ă͂����Ȃ�o�ꂷ��Ƃǂ��������̂��Ƃ܂ǂ��z�u��������Ȃ��B��{�́u�P�{�r�v������i�Q�o���v���C�Ȃ�u�V�{�r�v���E��j�Ŏ��A�c��̌��Ղ������Е��̎�Ŏ��B����������ɑΉ��ł���悤�ɗ��K���Ă��������^�w�B�S���ߖڂ̊K�i���ʂ́A�ȉ��ɂ�܂��̉^�w�@���Љ�Ă����B�i���F������A�����E��j
�T���P���Q���S���U���R���T���V���Q���R���S���T���U
�@�����Ձ�
���Ղ́A���ʂɓ�����ʔz�u�͓��ɓo�ꂵ�Ȃ��B�G�L�X�p�[�g���[�h�Ȃ�A���̕����ŃQ�[�W�̃`�����X�ł���B�t���R���{���[���_���Ă�����̂ŁA�ЂƂ�����Ă������������B���ʂ͊��������Ă��������B
�@���I�Ձ�
�I�ՂɂȂ�ƁA�₦�ԂȂ��I�u�W�F���~���Ă��Ă��Ȃ�Z�������ʂ��o�ꂷ��B���̂����A�Ō�ɓo�ꂷ�镈�ʂ��Љ��B
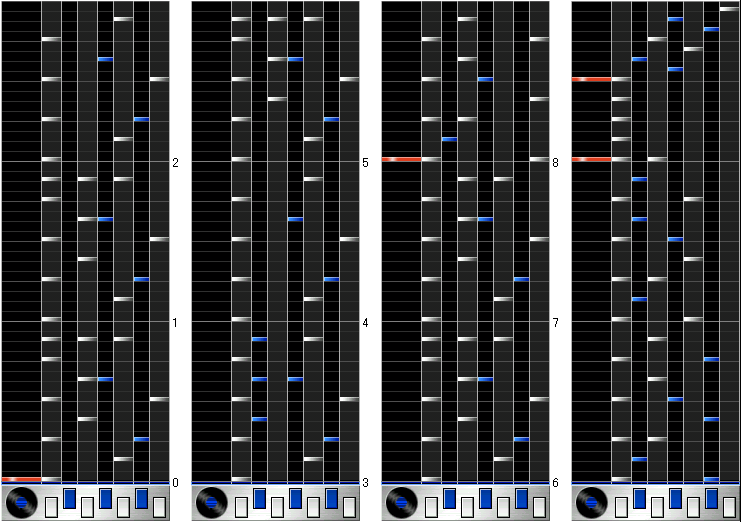
�P�P���߂܂ł́A�P�`�R�ԂŊ�{���Y��������ł���Ƃ���ɒ��ځB�܂��A�W���ߖڂ܂ł͂S�`�V�Ԃ������z�u�̂���Ԃ��Ő��藧���Ă���B�Ƃ����킯�ŁA�W���ߖڂ܂ł͓��ɉ������͂Ȃ��B�����A�a�o�l�̍����ɘf�킳���Ƃ����{���{���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���Ղ��璆�Ղ܂ł�ʂ��āA�Ȃ̑����Ɋ���Ă������ƁB�X���ߖڂ���P�P���ߖڂ́A�P�`�S�Ԃ̓��Y�����ꏏ�B�E��S���̌��Ղ��V����U�C�T�Ɉڂ��Ă��������ł���B�P�Q���ߖڂ̊K�i���ʂ́A�E���̌��ݑł��ŊȒP�ɔ������邪�u���������v�̉^�w���X���[�Y�ɂł��Ȃ��Ƃa�`�c�A���ő����Ȃ̂ŁA���Պ��o���}�X�^�[���Ă������B
��P�V��@�����e�[�}�Fstarmine�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���T���i���j
��ʂ���̌���ɂ����^���ꂽ�y�Ȃł���B�a�o�l�͂��Ȃ荂�߂����A�n�b�s�[�n�炵���m���̂悳�͑S�y�Ȓ��ł��P�C�Q�𑈂��B�����f�B���C���̌��Քz�u�ɂ��������̂́A�����I�ȓ�Փx�͌����č����Ȃ��B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
���̋Ȃ̃T�r�ɓ����镔���̕��ʁB
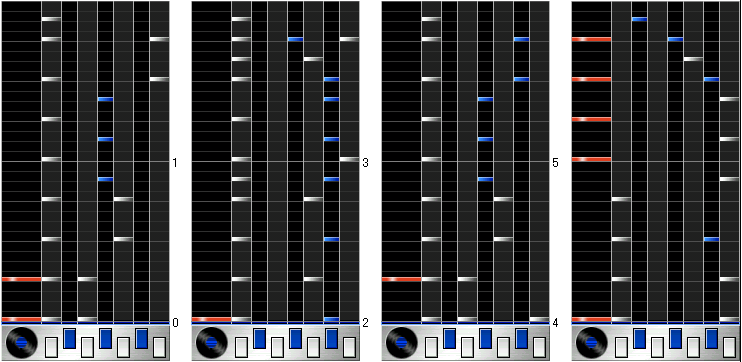
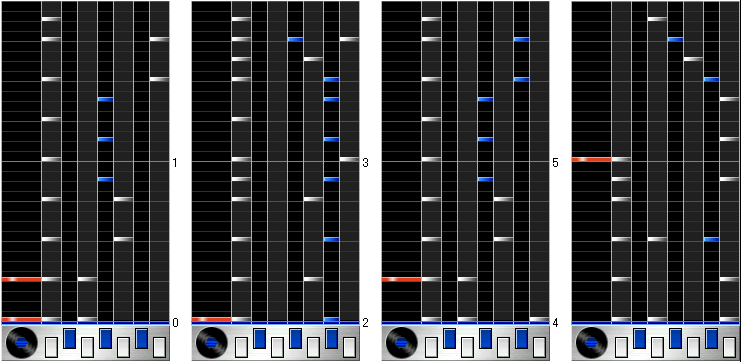
�P�Ԃ����Y���p�[�g�A�Q�`�V�Ԃ������f�B���C���Ƃ����A�킩��₷�����Քz�u�ł�����̂́A��i�W���ߖڂɂ���悤�ȃX�N���b�`�ƃ����f�B���C���̕��������͊���Ȃ��Ɠ�����Ǝv���B�P���ȂW���̊K�i�����Ȃ̂����A���̌��Ճp�^�[���͍�����o�ꂷ��̂ŗ��K��ς�ł��������B
�@�����Ձ�
���Ռ㔼�ɏo�Ă���A�ȉ��̕��ʁB
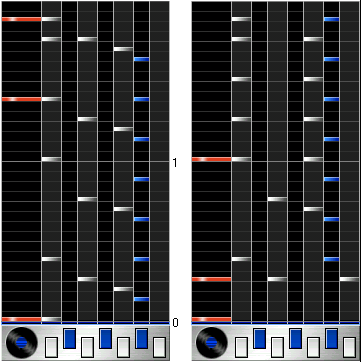
�P�E�R�Ԃ�����A�T�`�V�Ԃ��E��Ŏ��̂����A�R���ߖڂ̂Q���ڂɂ��āA�P�o���v���C���[�̓X�N���b�`���ǂ���邩���ۑ肩������Ȃ��B�R�ԁ{�X�N���b�`�������ɏo����悤�A�L�[���X�N���b�`����K���Ă������B���ɂ́A�R�E�V�Ԃ��E��Ŏ���Ă��܂����@������B���Պ��o���}�X�^�[���Ă���l�Ȃ�A������̕������������Ȃ��̂ł��E�߁B�Q�o���v���C���[�ɂƂ��ẮA���ɖ��̂Ȃ������ł��낤�B
�@���I�Ձ�
�Ō�̍Ō�ɓo�ꂷ��A�ȉ��̂悤�ȕ��ʁB
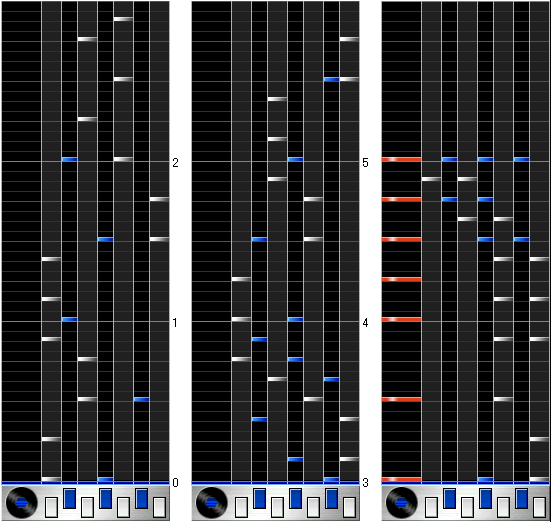
�����܂ł��Ȃ��A���ƂȂ镔���͂W�E�X���ߖځB�Q���̊K�i�����Ȃ̂����A�������͌��Պ��o���o���Ă��炤�����Ώ��@���Ȃ��B���炭�̊Ԃ�EASY�I�v�V�����v���C�ŗ��K���Ă݂悤�B�������́A���ʂ����Ȃ���C���[�W�g���[�j���O�����Ă݂�̂��ǂ����@�ł���B
��P�U��@�����e�[�}�FFinal Count Down�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���R���i�y�j
��܂��C�`�����̃��[���r�[�g�B�Ȓ��ɓo�ꂷ��M�^�[�̉��F���A��胁�^���F�����߂Ă���A�܂��ɁuMETALIC EURO�v�B������m���A�����̃J�o�[�Ȃ������Ǝv�������A�ڂ����͖Y�ꂽ�i���j�B4th style�́��~�V�̋Ȃł́A��Փx�I�ɈՂ������ł���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
���Ղ̗v���ӕ��ʂ́A���̕����B
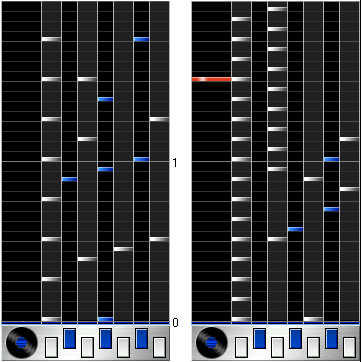
���̃t���[�Y�́A���̂��Ƃɂ����Քz�u��ς����`�œo�ꂷ��B�Ȃ�ƂȂ��\�z�͂ł���Ǝv�����A����łP�Ԃ̊�{���A����ȊO�͑S�ĉE��Ŏ��B�������A�S���ߖڂ̂P�E�R�Ԃ̂P�U�����݂͍��肾���Ŏ�邱�ƁB�P�o���v���C���[�́A�r���̃X�N���b�`�̕����ŗ���̌��݉����ɃX�C�b�`����A�X���[�Y�ɃX�N���b�`�ƘA�ł�����͂��B�Q�o���v���C���[�͌����܂ł��Ȃ�����݂̂Ō��݉����A�E��ŃX�N���b�`����邱�ƁB
�@�����Ձ�
���Y�~�b�N�ȕ��ʂ��炢���Ȃ��]���ĂP�U���������o�ꂷ��A�ȉ��̕��ʁB
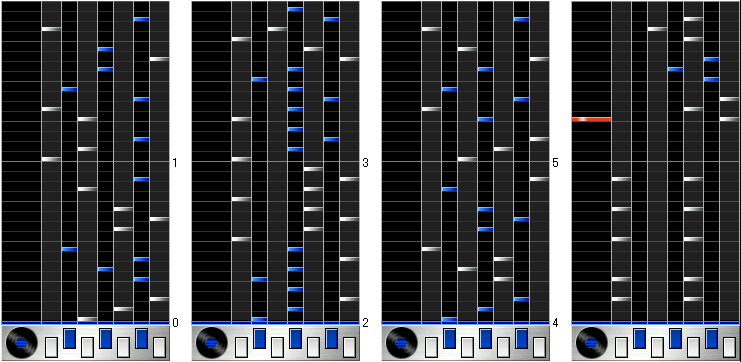
�P���ߖڂ̂P���ڂɃX�N���b�`������̂����A���ʍ쐬�i�K�œ���Y��Ă��܂����̂ŁA�����ŕt�������Ă����B���Ă��̕����A�O�X���B4U�ŏЉ���u�S���V�v�̌��݉������o�ꂷ��B�R�E�S���ߖڂ̉^�w�Ƃ��ẮA��{�S���ɓo�ꂷ��Q�ԁE�P�Ԃ�����ŁA�u�S���V���S�v�u�T���V���T�v�u�S���U���S�v�̂P�U���������E��ŁB�܂��A���̂��Ƃɓo�ꂷ��u�Q���S���V���T���P���R���U���S�v�́A���E���E�E�E�E�E���E���E�E�E�E�ŃX���[�Y�ɔ�������B�T�E�U���ߖڂ͂P�E�Q���ߖڂ̕ω��^�Ȃ̂ŁA���Ȃ��ł��낤�B
�܂��A���̐����ߌ�ɓo�ꂷ��ȉ��̕��ʂ������������������B
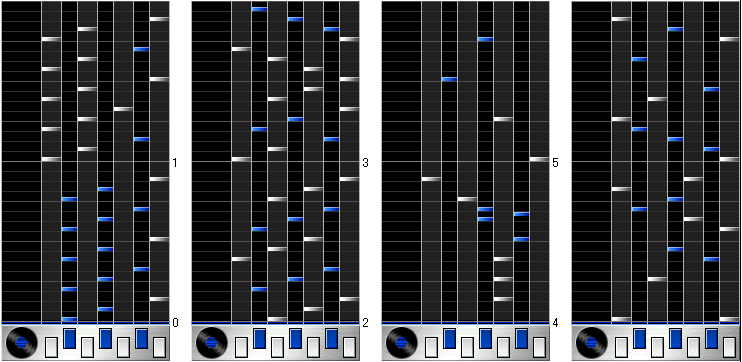
�������胊�Y��������āA�P�U�������ł��邱�Ƃ��ӎ����Ȃ���@�����B�P���ߖڂ́u�Q���S�v�͍���A���Ƃɑ����U�ԁE�V�Ԃ͉E��B�Q���ߖڂ��P���ߖڂƓ��l�Ɂu�P���R�v������A����ȊO�͉E��B�u���������E�v�̂���Ԃ��Œʂ蔲���Ă������B�S���ߖڂɂ��ẮA�ȉ�����܂��̉^�w�B
�P���R���U���Q���S���V���R���T���V���T���R���P���V���U���S���Q
�i���͉E��A���F�͉E��ŒS���j
�@���I�Ձ�
�I�Ղ́A���ՂƓ����t���[�Y�ŁA���Քz�u���ς�����p�^�[�����o��B�Ō�ɓo�ꂷ��P�U�A�I�u�W�F�́A�E�����̌��݉����Ŕ�������B�A�^�}�̂��܂��ɂ��Ă���U�Ԃ���肱�ڂ��Ȃ��悤�ɁB���ʂ͊��������Ă��������B
�@�`�Ō�Ɂ`
���̋ȁA��Փx�I�ɂ������҂̃��x���A�b�v�ɓK���Ă���Ǝv����̂ŁA���̋Ȃŗ��K��ς�ł݂Ă͂��������낤���B���ɂP�U�A�t���[�Y�Ō��O���[�g��A���ł���悤�ɂȂ��Ă���A�X�R�A�A�^�b�J�[�Ƃ��Ă����Ȃ�̗͂����Ă���ł��낤�Ǝv����B�t���R���{���[���_����̂ŁA���ЂƂ�������Ă������������B
��P�T��@�����e�[�}�FGet on Beat�`WILD STYLE�`�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���Q���i���j
�UDX2nd�Ɏ��^����Ă���uGet on Beat�v�̃A�����W�o�[�W�����B���Ȃ��n�[�h�ȋȒ��ɃA�����W����Ă���A��Փx�����Ȃ�̂��̂ł��낤�B�������A���̋Ȃɂ���͂��{�̃��Y���p�^�[�������݂��A����������ł��܂���������ƍU���̎����������̂ł͂Ȃ����낤���B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
�܂����ՂŖ��ȕ������A�ȉ��̕��ʁB
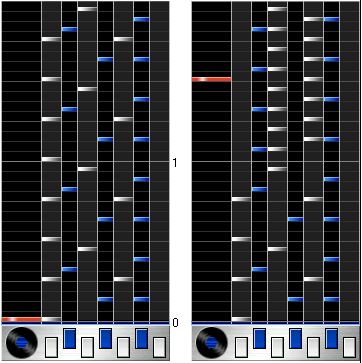
�P�`�R���߂͓����z�u�̂���Ԃ��B���̕����͂S�E�T�E�U�Ԃ��E��ŁA�P�E�Q�E�R�Ԃ�����Ŏ��B�����̃��Y���p�^�[���͂��̐���o�ꂷ��B�P�U���̃n�l���ӎ����āA������Ǝ���悤�ɂȂ��Ă��������B�܂��S���ߖڂ̂P�U�A�I�u�W�F�����A�ǂ����Ă��S�����Ȃ��l�́A�X�N���b�`�����悤�B
�@�����Ձ�
���Ոȍ~�̊�{�p�^�[���ƂȂ�z�u���A�ȉ��̂��́B
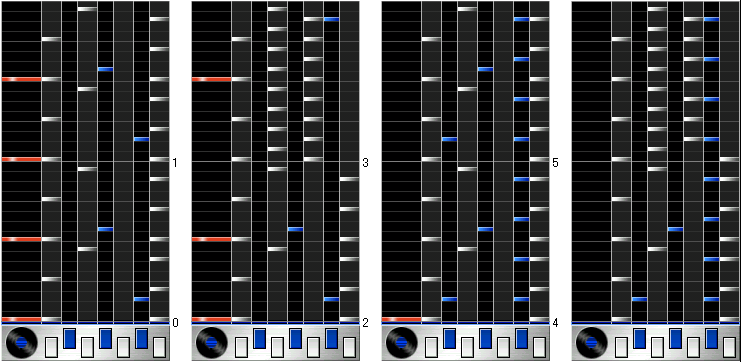
��{���Y�����R���ߑ����āA�S���ߖڂɂP�U�A������p�^�[���ł���B�P�`�R���ߖڂ���{�p�^�[���Ȃ̂ŁA���ЂƂ������͒@����悤�ɂȂ肽���B���̕������ɂ�݂A�T�`�V���ߖڂɖڂ������Ă݂�Ɓc�X�N���b�`�������āA�Q�E�U�Ԃ�������Ă��邾���ł���B�U���̎���Ƃ��ẮA�E��ł�������U�E�V�Ԃ�����悤�ɗ��K���邱�ƁB�c�������Ղ͍��肾���ŏ[����邱�Ƃ��ł���B�����āA�S�E�W���ߖڂ̂P�U�A�����A�P�E�R�Ԃ�����Ŏ��B�S���ߖڂ̓X�N���b�`�������Ă��Ă����Â炢��������Ȃ����A�A�ł������������̂Ȃ�X�N���b�`�͖������Ă��S�R���܂�Ȃ��B�����ɂ����ł���U�Ԃ��A�T�Ԃƈꏏ�ɉE��Ŏ��Ή��̖����Ȃ��B
�����āA�r���Ɍ����X�N���b�`���S�̈ȉ��̕��ʁB
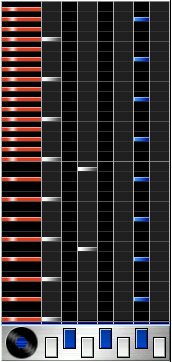
�P���ߖڂ̓L�[���X�N���b�`����g���ĂȂ�Ƃ�����Ŏ�邱�Ƃ��\�����A�Q���ߖڂ͂�͂�Ў�Ō��Ղ��������������m�ɒ@����B�P���U�ƁA��◣�ꂽ���Ղ̌��݉��������A���������Ў�̐e�w�Ə��w�̕��Ŋ��o���o���Ă��܂��ƁA�ȒP�Ƀ}�X�^�[�ł���B�Ȃ��A���Ղ͂W�������ŃX�N���b�`���P�U�������Ȃ̂ŁA�ǂ��炩�̎�̓����ɂ��Ȃ��悤�ɂ��悤�B
�@���I�Ձ�
���ՂŏЉ�����Y���p�^�[���̔h���^���o�ꂷ��B���Y���������������Œe�����Ȃ��Ζ��͂Ȃ��ł��낤�B���ʂ͊��������Ă��������B
�@�`�Ō�Ɂ`
���̋ȁA�Ԃ����Ⴏ���b����{�p�^�[�������o���Ă��܂��ǂ�ȂɑO���Ŏ��s���Ă��A�㔼�Ŏ��Ԃ����Ƃ��ł��Ă��܂��B�I�Ղ̃I�u�W�F�z�u�͂������Ƀ��N�ɒe�����Ȃ���悤�ɂȂ�ɂ͎��Ԃ�������Ǝv�����A�p�^�[����c�����Ă��������A���ʂ��o����̂��ȒP�ł���B���Ղ̕��ʂ��Q�l�ɂ��āA���Ոȍ~�̃}�X�^�[��ڎw���悤�ɂ��Ăق����B
��P�S��@�����e�[�}�FB4U�@�U���@�Q�O�O�P�N�R���P���i�j
beatmania�ADDR�Ƃ��ɐl�C�������ȁBbeatmania�ɂ����Ă͂��̓�Փx�̍�������R�A�ȃv���C���[�ɐ��Ȑl�C���ւ�B�Ȏ��́ADYNAMITE RAVE��Burnin' the floor��肢�������A�b�p�[���������A���ЂƂ��U�����Ă݂����Ȃł͂Ȃ����낤���B���Ȃ݂ɂ��̋Ȃ�Another version�́u�Q�o���v���C���[�E���v�Ƃ��č����ȃI�u�W�F�z�u�ƂȂ��Ă��邪�A�P�o���v���C�ł����\���т����C������c�B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F�����������������@
�@���`������
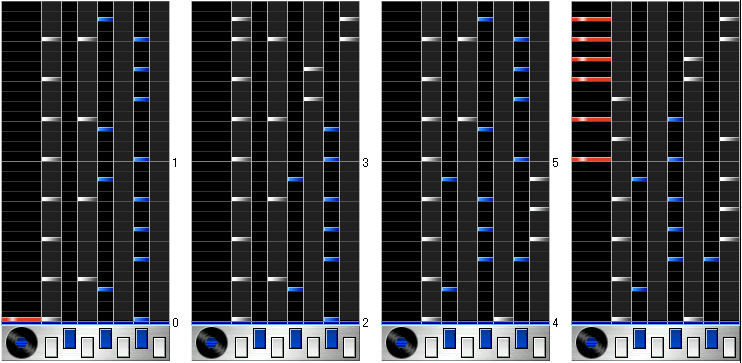
�Q�R�[���X�ڂ́A����̕ω��^�̃I�u�W�F�z�u���o�ꂷ��B�I�u�W�F���S�Ƃ��Ă͂P�`�R�Ԃ�����A����ȊO�͉E��ł���B�T���ߖڈȍ~�ɏo�Ă���A�V���S�̂P�U�������́A���̋Ȃł����p���邱�Ƃ������̂ŁA���ЉE�肾���łł���悤�}�X�^�[���Ă��������B
�@���T�r��
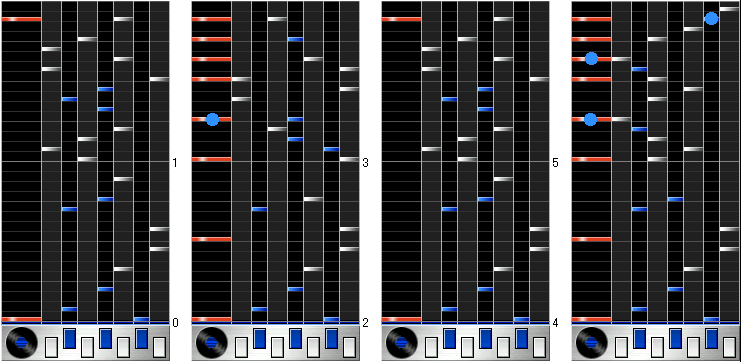
�f���I�ȃX�N���b�`�ƊK�i�z�u�̃I�u�W�F���ȎҁB�Q�R�[���X�ڂ͂W���ߖڂ̌��Ղ������قȂ���̂́A�S�������悤�ȃI�u�W�F�z�u���o�ꂷ��B���ɂ��̕����́A�Q�o���v���C���[�͌��Ղ�����ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�E�����̕��͂���ۂǃX���[�Y�ɍ���w�������悤�B������K�v������B�Ȃ��A���S�ҁ`�����҂̕��ɂƂ��ẮA�ƂĂ�����Ȕz�u���������Ȃ��ɂ͎��Ԃ�������Ǝv���̂ŁA�I�u�W�F�����𗘗p���Ă��߂����Ă݂悤�B��������|�C���g�́A�S���ߖڂƂW���ߖځB�S���ߖڂ͂Q�ڂ̃X�N���b�`�����āu�V���U���S���R���S�v�̊K�i���ʂ��������藼��łƂ�B�W���ߖڂ͂�����Ɠ����������Ȃ����A�܂��Q�ڂ̃X�N���b�`�����čŏ��́u�R���T���R���Q���P�v���Ƃ������ƁA�������S�ڂ̃X�N���b�`�����Ď��̊K�i���Ƃ�A�Ō�́u�R���T���U���V�v�͂U�Ԃ�����B����ȊO�͑S������͂��B�i��̕��ʂŁA���F�́��œh��ꂽ���ʂ������I�u�W�F�ł���B�j
�@���a������
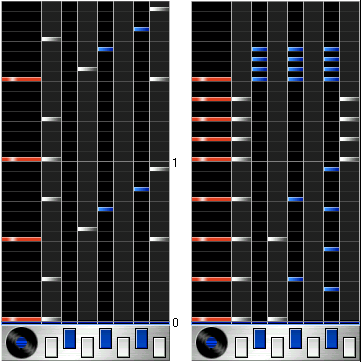
�P�o���v���C���[�ɂƂ��Ă͓��ɖ��͂Ȃ��ł��낤�B�Q�o���v���C���[�́A�R���ߖڂ̃X�N���b�`�������Ƃ�Â炢��������Ȃ��B�����͏ł炸�A�U�ԂƃX�N���b�`�������Ŏ���Ă��蔲���悤�B�����������ƁA�Ăя�ŏЉ���T�r�t���[�Y�̕ω��^���o�ꂷ��B�W���ߖڂ̃X�N���b�`�p�^�[�����ς���Ă���̂ŁA�v���ӁB�����ł͂��̕����̕��ʂ͊��������Ă��������B
�@�`�Ō�Ɂ`
�T�r�����ŏЉ���I�u�W�F���������A�Q�l�܂łɂW���ߖڂŃX�N���b�`��S���������Č��Ղ�S�Ď�����ꍇ�A���������R�O�`�S�O���iEASY�I�v�V�����Ȃ�Q�S�`�R�Q���j�̃Q�[�W�������m�F����Ă���B�i�X����➑̐ݒ�ɂ���āA�Q�[�W�����̕��͈قȂ�j
��P�R��@�����e�[�}�FABSOLUTE�@�U���@�Q�O�O�P�N�Q���Q�V���i�j
beatmania 4th style�Ɏ��^����Ă���y�Ȃ̒��ł��A��܂���Ԃ̂��C�ɓ���̊y�ȁB���~�V�̋Ȃ̒��ł�����قǓ�Փx�������Ȃ��A���Ȃ�l�C�̂���Ȃł͂Ȃ����낤���B�����ł́A����Ȑl�C�̍����Ȃ����ЂƂ��݂Ȃ���ɍU�����Ă������������A�|�C���g�ƂȂ镔���̕��ʂ𑽂߂ɏЉ�邱�Ƃɂ������B
����܂��I�y�ȓ�Փx�]���F���������������@
�@�����Ձ�
���̊y�Ȃ̊�{�t���[�Y�ƂȂ镈�ʂ́A�ȉ��̂��̂ł���B
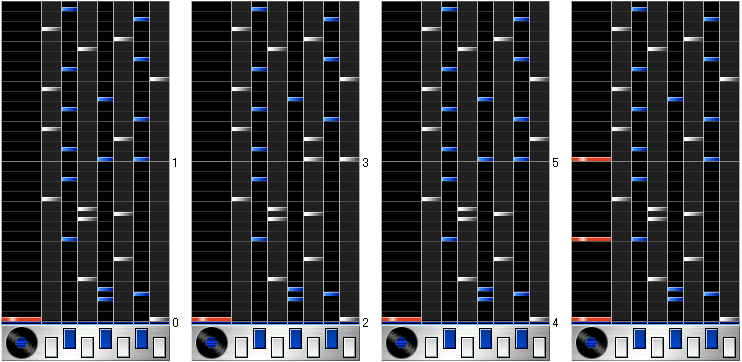
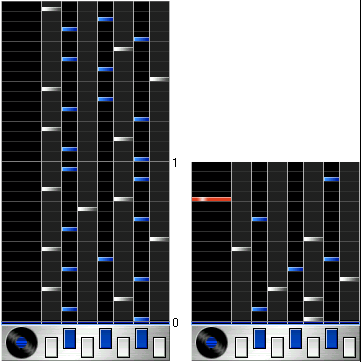
��i���ʂ̂P�E�Q���ߖڂ��A���ՂƏI�Ղ̊�{�t���[�Y�ł���B���ɂQ���ߖڂ̂P�U�A���ʂ́A�Ƃ���ǂ���Ńp�^�[����ς��Ȃ���o�ꂷ�镈�ʔz�u�Ȃ̂ŁA���Ѓ}�X�^�[���Ă����������ʂł���B��i���ʂɌf�����Ă���S�p�^�[�����悭����ׂĂ݂Ă������������B�܂��A���i���ʂ̕��͏�ł̂P�U�A���ʂƂ܂������p�^�[�����Ⴄ���A����قǓ���z�u�ł��Ȃ��ł��낤�B
�@�����ՑO����
���Ղɓ����Ă����́A�ȉ��̂悤�ȕ��ʁB
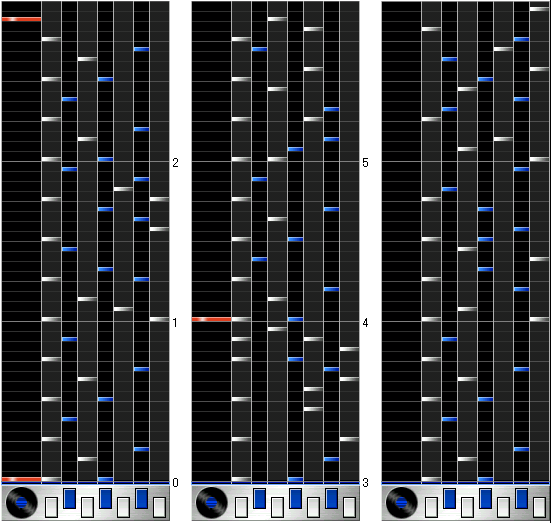
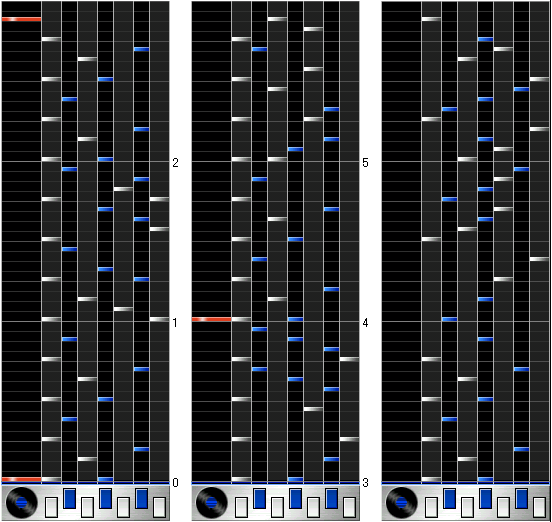
�P�Ԃ͏�ɂS���̊�{���B����ȊO�̂U�̌��Ղ́A�ł��邾���E�肾���ł����悤�ɂ������B�o���o���Ȕz�u�̂悤�Ɍ����邪�A���ۂ͏�i�E���i�Ń��Y���p�^�[���͕ς���Ă��Ȃ��B�i���c�W�E�X���ߖځj���̒ʂ�A���̋Ȃł̓��Y���p�^�[���������ŁA�@�����Ղ��قȂ邾���̕���������Ԃ��o�ꂷ��B���Ȃ킿�A��{���Y�������߂A�������Y���p�^�[���ł��鑼�̕��ʂ������}�X�^�[�ł��邱�ƂɂȂ�B
�@�����Ռ㔼��
�����ЂƂA���Ղŏd�v�ȕ��ʂ́A�ȉ��̒ʂ�B
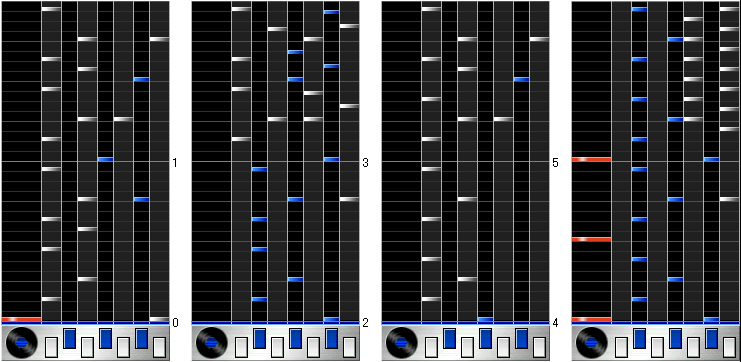
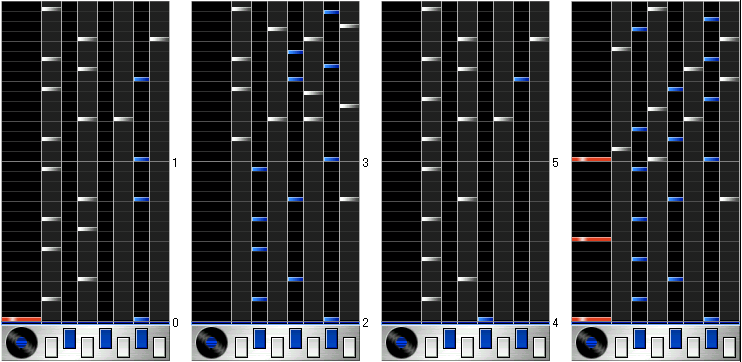
�������A��i�Ɖ��i�Ŕ�ׂĂ݂�ƁA�W���ߖڈȊO�̓��Y���p�^�[�����ꏏ�ł���B�P�`�R�Ԃ͍���ŁA�S�`�V�Ԃ͉E��Œ@�����B�܂��A��i�E���i�Ƃ��S���ߖڂ͏����^�C�~���O���Ƃ�Â炢���ʂɂȂ��Ă��邪�A����i�P�`�R�ԁj�̃��Y���p�^�[���͂����Ɠ����ŁA�E��i�S�`�V�ԁj�͂R�A���̃^�C�~���O�őłƂ��܂����z������B��i�W���ߖڂ̂T�E�V�Ԃ̌��݉����́A�����^�C�~���O������邾���ła�`�c�A���Ƃ������|�̃]�[���ł��邪�A�����̂V�Ԃ�����Ƃ��܂��^�C�~���O�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���I�Ձ�
���Ղ̕��ʃp�^�[�������ω����������ʂ��o�ꂷ��B�����ł͕��ʂ͊��������Ă����������A��{�͏��ՂƓ����Ȃ̂ŁA���ɖ��͂Ȃ��ł��낤�B�Ȃ��A�Ō�̏�ʂł͂���a�o�l�������Ă����Ƃ����A�ς�������o���{����Ă���̂ŁA����̃v���C�ł͎d�����Ȃ��Ƃ��āA�Q�x�ڈȍ~�̃v���C�ł͂����ň���������Ȃ��悤�ɂ������B
�@�`�Ō�Ɂ`
���܂ł̃��|�[�g������╈�ʂ̐����������߁A���S�ɂ��̃y�[�W���J���܂łɏ������Ԃ��������Ă��܂����Ƃ������ł��l�т��Ă����B