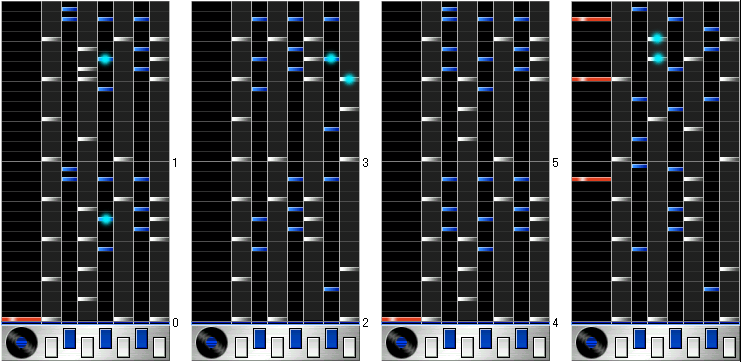
第53回 研究テーマ:THE SAFARI 攻略 2001年6月30日(土)
3rd styleに初登場して以来、数多くのプレイヤーを悩ませてきたであろう問題作と言える楽曲。3rd styleの隠し曲に指定されており、その出現条件は1曲中で555コンボ以上つなげてクリアするというものであった。曲自体はやまきもとてもお気に入りなのだが、当時のレベルから考えると凶悪の極みとも思えるその譜面配置は時を経た今でもかなりの難易度評価をマークしており、つい最近やっとクリアできたのだ…というわけで、中級者程度のレベルのプレイヤーがクリアするにあたって注意したい部分をかいつまんで解説していこうと思う。譜面はこちらをどうぞご覧いただきたい。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★★★>
<序盤(1段目1小節目〜4段目4小節目)>
最初からいきなり度肝を抜かれる方もおられるかもしれないが、最初の4小節までの運指はほとんどワンパターン。ネックとなるのは「1・4・5・7+S」の運指。やまきの場合は1・4・5番を左手で、7番とスクラッチを右手で取っている。これは2P側プレイの場合なので、1P側プレイの人には適用できない。この4小節を越えれば、しばらくはゲージを伸ばせる程度に簡単な譜面なので、取りこぼしをしないように。
2段目の5小節目から、本格的に難しい譜面が登場し始める。2段目5小節目から3段目4小節目はこの曲に登場するフレーズの基本パターン。ここまでくらいは取りこぼしがない程度になっておきたい。ネックの配置は「1・3・5・6・7+S」(2段目5小節)だが、ここはまぁ2P側であれば問題ないと思われる。やまきの運指法は1・3・5番を左手で、6・7番とスクラッチを右手で。1P側プレイならば、6番を無視すればあっさり抜けられる。これと似たパターンで、3段目1小節にも「1・5・6・7+S」という配置があるが、これは言わずとも問題なかろう。1P側でも5・6・7番を右手で取れれば全部取ることが可能。
3段目5小節目から4段目4小節目まで。「何だこりゃ?」と思う方も多いと思う。ただしこれは譜面を見て直感的に全部のオブジェを取ろうと考えたときに「何だこりゃ?」なのであって、こんなもの、ある程度のオブジェを無視していかなければ中級者には攻略は無理であろう。実際、やまきもオブジェを無視しまくっている。。
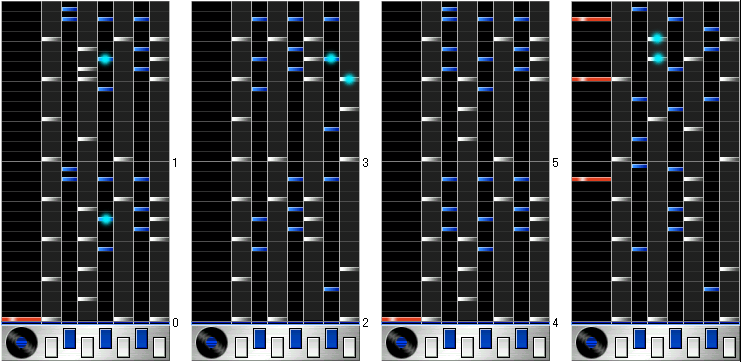
ここに、あらためて3段目5小節目から4段目4小節目までの譜面を再掲する。図中、水色の●で塗られたオブジェは、やまきが無視しているオブジェ。運指の基本は、1〜3番を左手で、4〜7番を右手で。ところどころに登場する「7→6→7→6→7」や「5→4→5→4→5」は、できれば譜面通りに叩きたいが、どうしても左手とのタイミングがずれてしまうという人は2鍵盤の同時押しでごまかして抜けてしまおう。この戦法、この曲を攻略する上では非常に有用なので、階段部分などで手が届かなそうだと思ったら同時押しに切り替えてしまおう。
<中盤(4段目5小節目〜6段目5小節目)>
4段目5小節目から5段目4小節目までは回復ゾーン。ここでゲージを減らしてしまうという方は、譜面をよく把握してからチャレンジした方がよい。ここである程度ゲージを伸ばさないと、先がきびしいからである。2カ所で登場する「6→5→6→7→6→5(7)」の階段譜面は、右手オンリーでスムーズに取れるようになっておきたい。そして5段目5小節目から再び「何だこりゃ?」譜面が再登場。5段目5小節目に限っては、3拍目手前の2番だけを無視すればうまく抜けられるだろう。
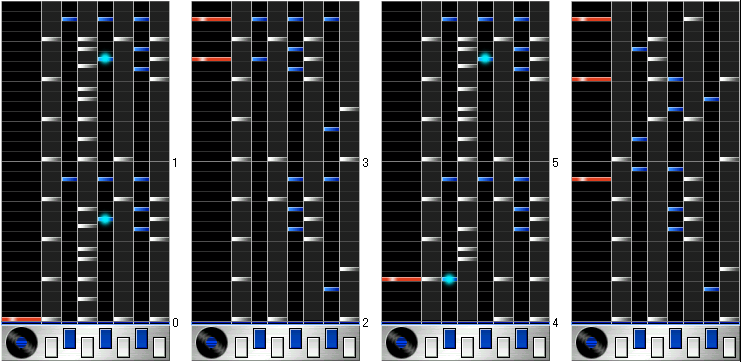
上は、5段目6小節目から6段目5小節目までの譜面再掲。例によって、水色の●で塗られたオブジェがやまきの無視オブジェ。その他の留意事項は、序盤で紹介したとおり。なお、2P側プレイの場合を想定したものなので、1P側プレイヤーは無視オブジェの位置その他が変わってくる可能性もある。譜面をよく見て研究してみていただきたい。
<終盤(6段目6小節目〜7段目5小節目)>
中盤までをそこそこのゲージ残量で抜けることができるならば、終盤はもう攻略できたも同然。依然難易度の高い譜面は続くが、中盤などで紹介した程度の譜面である。7段目2小節目の時点で70%もゲージが残っていれば、クリアは目前。譜面については、中盤で紹介したものを参考にしていただきたい。無視するオブジェなどもこれに準じる。なお、ここで紹介した方法で攻略した場合、EASYオプションをつけなくても100%クリアが可能であることはやまき本人が確認済である。まずは、クリアを目指して頑張っていただきたい。
第12回 研究テーマ:CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 攻略 2001年2月25日(日)
beatmaniaに収録されているユーロビートの中でも、やまきお気に入りの曲。ところどころに登場するシンセタムの16連打がやや曲者だが、ぜひともマスターしたい曲であろう。難易度の高いと思われるポイントを中心に説明してみよう。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★☆>
<序盤編>
序盤でやや厄介と思われる場面は、以下の部分だろうか。

この場面の最後にもタムの16連打がからんでいるが、それ以外の部分も慣れないと叩きづらい譜面である。1番は基本の4拍、それ以外は見たカンジちょっと複雑なリズムを刻んでいるのだが、ここは基本拍を左手で、それ以外を右手でこなす。最後のタムの連打は、譜面を見て焦りながら叩くと、ややタイミングが早くなりがちなので、落ち着いてゆっくりめにこなすように心がけてみよう。
<中盤編>
中盤で出てくる厄介な譜面は、以下の2つであろう。

どちらも連打がらみの譜面だが、左側の譜面は最初の4連オブジェは両手で交互打ち、あとはスクラッチを片手で取りつつ残りの連オブジェを片手で取る運指。右側の譜面は、やや2P側プレイに不利があるが、スクラッチを片手で、鍵盤はもう片方の手で取るのがよい。右に寄った譜面なので、2P側プレイの場合は、キー&スクラッチが完璧にできる人ならば鍵盤を両手で交互打ちで取りつつスクラッチを全部取ることも可能。初心者のうちは、スクラッチ無視で鍵盤を取りに行くのもあり。
<終盤編>
最後の方になって登場する、以下のようなオブジェラッシュが、終盤のカギ。

基本は、1〜3番の鍵盤を左手で、4〜7番の鍵盤を右手で取る押し方。最後の小節の16連打はもちろん、1番を左手で、16連オブジェを右手で取る。ここは序盤でも注意したとおり、落ち着いてゆっくり取ることである。
〜最後に〜
今回をもって、当研究所が用意した「beatmania 3rd style」の攻略記事は終了となる。次回からはいよいよ「4th style」の攻略記事に入る。ただ、今後もリクエストをいただけば「3rd style」の記事を用意したいと思っている。
第11回 研究テーマ:Presto 攻略 2001年2月23日(金)
beatmaniaシリーズに収録されているピアノ曲の中では1,2を争うほどの名曲。どこか西洋的な香りの漂うフーガであるが、ほぼ全譜面にわたって階段状の譜面が登場する。曲全体としては長い曲ではないので、ポイントを絞って説明してみたい。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★>
<ポイント1:序盤後半>
序盤を抜けてからの以下の譜面をご覧いただきたい。

この部分の基本は、拍のアタマを右手で、残りの部分を左手でこなす運指であろう。階段譜面の運指法を見極めるには、譜面をよく研究するのが一番である。なお、やまきの運指法は以下に挙げるとおりである。
1→5→3→5→6→5→3→5→7→5→3→5→7→3→1→3→
6→3→2→3→6→2→1→2→5→2→1→2→5→3→1→3→
1→5→3→5→6→5→3→5→7→5→3→5→7→3→1→3→
6→3→2→3→6→2→7→4→5→2→1→2→5→3→6→4
(運指凡例:白=左手親指、赤=左手人差し指、黄=左手中指、緑=右手人差し指)
<ポイント2:中盤後半〜終盤>
序盤を抜けると少し楽な譜面配置が続いたあと、以下のような階段譜面が続く。


ポイント1で述べたような単純な運指では、この部分はうまく乗り越えられない。この場面で特に重要なポイントは、11小節目の「6→7→6→5→4→3→2→1」という8連オブジェと、14小節目にある「7→6→4→3→2」の部分。前者は、ポイント1で挙げた譜面のあとにも登場するので、きちんと押せるようになっておきたい譜面配置である。また、後者は単純な16分譜面ではなく6連符のタイミングで押すと、うまく乗り越えられる。よく譜面を見て、自分なりの運指法を考えてみていただきたい。
第10回 研究テーマ:S.O.S.〜The Tiger took my family〜 攻略 2001年2月14日(水)
曲の速さもさることながら、横に広く広がった階段譜面が何といってもクリアの妨げになっている。ノーマルスピードでは譜面が見づらいし、ハイスピードにすると速すぎて手が追いつかないし…そんなあなたのために、特に練習すべき部分を採りあげてみたい。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★>
<ポイント1:Aメロ導入部>
まずは、こちらの階段譜面から。

運指のポイントは特にないのだが、こんな譜面がかなりのスピードで落ちてくれば、誰もが面食らうであろう。こういう譜面を攻略するための一番の練習法は、譜面をできるだけ覚えて、イメージトレーニングを行うことである。また、実際にプレイする上では、あまり鍵盤を叩くタイミングにこだわらず、取りこぼしを減らすように叩くことが重要である。タイミング良く叩く練習は、譜面をほぼ完璧にマスターしてからで充分であろう。
<ポイント2:中盤後半>
この曲はいくつかの譜面パターンのくり返しで成り立っている部分が多いのだが、ここで紹介する譜面は全体で1度しか出てこないものである。じっくり譜面を見て、イメージトレーニングをしていただきたい。

階段譜面と違って、基本リズムに乗った譜面となっているので、攻略にはそれほど苦労しないのではないだろうか。譜面を覚えてからチャレンジしてみよう。5〜8小節目でフルコンボができるなら、1〜4小節目の2番は無視しても大丈夫。1・2・3番の同時押しが片手でできない方は、5〜8小節目を特に練習して1〜4小節目でのゲージ減少をしっかりカバーできるようになろう。
〜最後に〜
こういった曲ははっきり言って、攻略記事の書きようがない。今回、その難しさというのを実感した。「こんなんじゃ、参考になんね〜よ!」とお怒りのみなさま、ホントに申し訳ございません。。
第9回 研究テーマ:Holic 攻略 2001年2月13日(火)
序盤・中盤と、かなりリズムが不規則な、珍しい楽曲である。ハードテクノとしてはbeatmania史上最難関の曲ではなかろうか。単純な4/4拍子でないところにやや違和感を覚えるが、その違和感以上に問題なのは、終盤にかかってからのオブジェラッシュにあるだろう。そのあたりを中心に攻略法を考えてみたい。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★☆>
〜序盤〜
7/8拍子という、変わったリズムであるが、特に大きな問題はないであろう。序盤のうちはフルコンボで通過できるくらいになっておこう。
〜中盤〜
拍子が14/8拍子になるのだが、意外と気づきづらいかもしれない。まぁ、下手にリズムの変化をつかんで頭が混乱するよりは、リズム変化も何のそので突っ走ってしまう方がクリアに近づくであろう。この中盤でやっかいな部分は、以下の譜面。

1・2・3番のコンビネーションを左手で、それ以外は右手で担当するのだが、右手担当の譜面は、この部分の直前の2小節と変わっていない。これを頭の片隅に入れておくと、スムーズに右手が動いてくれると思う。また、左手がスムーズに動かない場合は同時押しでくぐり抜けよう。2・3番の同時押しよりは、3・1番の同時押しの方が動きに無理が少ない。ちなみに、この部分を抜けたあともしばらくオブジェラッシュが続くが、こちらの方は比較的、譜面の見極めはラクであろう。ここでは割愛する。
〜終盤〜
さて、いよいよリズムも正則の4/4拍子に戻るのだが、そんなことはどうでもいいと言わんばかりのオブジェラッシュ。しかし、冷静に譜面を見ればそれほどきびしい譜面でもない。以下をご覧いただきたい。

中盤と同じく、1・2・3番を左手で、それ以外を右手で担当するのがいいであろう。よく見てみると、1・3番は最後の小節を除いて8分の交互打ちである。残った4〜7番の配置だけを見れば、思った以上に簡単であることに気づくのではないだろうか。この通り完全に鍵盤の担当を振り分けることでかなり余裕のある運指を実現できる。やや特殊なのが、4小節目と8小節目。4小節目では3・4番の16分を右手で叩く方がラクである。そして8小節目にいたっては、一瞬どう叩くか迷うところであるが、やはり1〜3番までを左手で叩くのがいいだろう。スカスカの譜面だが、リズム通りに叩くのはかなり至難の業。初めは同時押しでもいいので、無視するオブジェ数を減らしていくようにしよう。ここの部分だけに関して言えば、右スクラッチの方が幾分か有利かもしれない。この部分を、残りゲージ60%以上で抜けることができれば、クリアは目前である。
〜最後に〜
この曲は、3rd styleの☆×6の曲の中で、やまきが一番苦労した曲である。ここに紹介した方法は、苦労した末に苦肉の策で考え出した攻略法なので、運指法などやや無理のあるところも出てくると思うが、そこはぜひやまきの方法も参考にしつつ、みなさんなりの方法でくぐり抜けていただきたい。また、本来ならこの曲の譜面をまるまる紹介したいのだが、スペースの関係上、実行できなかった。いずれ機会があれば、全譜面紹介したいと思っている。
第8回 研究テーマ:era〜Nostal mix〜 攻略 2001年2月12日(月)
ⅡDX3rdの中でも、かなり人気の高い曲のようだが、難易度もかなり高い。その原因となっているのは、何といっても中盤〜終盤のオブジェラッシュにあるのではないだろうか。ここではその部分を中心にして、クリアを目指すための攻略法を考えてみる。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★>
〜序盤・中盤前半〜
序盤はさほど注意しなければならない点はない。やや曲のテンポが速いかもしれないが、オブジェ数としてはそれほど多くなく、込み合った譜面でもないので、2〜3回もプレイすればほぼ完璧に押せるようになるであろう。問題は、BPMが変化したあとである。しばらくのうちはBPMが急に半分になることにとまどってしまい、ここでメロメロになってしまうパターンもある。しかもこの部分、ノーマルスピードでプレイしているとかなり込み合った譜面で表示されるため、ここをまず攻略したいという方は、ハイスピードでプレイした方が絶対によいと思う。
〜中盤後半〜
ここでまたBPMが元に戻り、やはりとまどうことになる。しかも前半までの甘い譜面ではなく、かなりオブジェ数も増えて16分の刻みが基本になる。まずは、BPMが戻った直後の譜面を見てみよう。

縮小をかけているため、やや見づらい譜面になってしまっているが、ここの攻略のポイントとして、まずはスクラッチを無視して鍵盤の配置を覚えてしまおう。この部分の7〜8小節目にある、3・5・7番中心の16分刻みは、途中に紛れ込んでいる1番を無視すれば比較的楽に通り越せるはず。
〜終盤〜
上の譜面以降、4小節は比較的押しやすい譜面となっている。ここでは割愛させていただくが、この部分はゲージ回復ゾーンと考えていただきたい。ここで少なくともゲージを90%以上残しておきたいところである。そして、最後のオブジェラッシュ。初めてプレイする方は、ただただ唖然として何もできないまま終わってしまうのではないだろうか。ここでは、その部分の譜面を掲載する。

こうして譜面で見てしまうと、かなり簡単に押せそうに見えてしまうが、けっこう厄介な代物かもしれない。ただ、1〜3小節目までは基本拍が全て1・5番であるところに注目。変化しているのは裏拍のみである。そこでここは、表を左手で、裏拍を右手で担当する方法がいい。左手は常に1・5番同時押しで、右手は青鍵盤を中心に取りこぼしを徐々に減らすよう練習する。そして、この部分の4小節目については、最初のうちはやはりスクラッチよりも鍵盤を完璧に取れるようにしよう。この曲のきびしいところは、この部分を抜けるとオブジェがほとんどないため、あとで回復が効かないところである。かといって、初めのうちは無理して全部取ろうとすると、途中でわけがわからなくなってしまうという最悪のパターンを招きかねない。そこで、無視するオブジェをあらかじめ決めてしまおう。こうして譜面で見てみると、1〜3小節目において3番のオブジェ数がやや少ないようだ。すなわち、3番のオブジェなら無視してもゲージの総体的な減少は少なくて済むはずである。さすがに4小節目で無視オブジェを決めるのは、クリアを決める大事な部分であるだけに慎重にならざるを得ないが、慣れてきたら全部取ることもできるだろう。ここは要練習ポイントである。
〜最後に〜
難易度の高い、曲後半部分を中心にレポートしたが、前半もなめてかかっているとけっこう痛い目を見るかもしれない。BPMが変化する曲中盤まではフルコンボを目指してがんばってみよう。また、LIGHT7キーモードを活用するのもよい練習になることと思う。やまき的にイチ押しの曲でもあるので、ぜひクリアを目指していただきたいと思う。
第7回 研究テーマ:R5 攻略 2001年2月9日(金)
さて、今まではⅡDXの基礎的事項をレポートしてきたが、今回からはⅡDXに収録されている楽曲の中で、攻略が難しいと思われるものにスポットを当てて、ポイントごとの攻略方法を考えてみたいと思う。ただし、ここに紹介する攻略法は「クリアを目指す」ための攻略法の一例であり、さらなるレベルアップを目指す方はここに紹介した攻略法に甘んじることなく、研究と練習を重ねて自分なりの攻略法を見つけだしていただきたい。このページはあくまで、楽曲クリアのための踏み台として捉えてほしい。
<やまき的楽曲難易度評価:★★★★★★>
〜序盤編〜
序盤については、特に述べるべき事項はないであろう。プレイを重ねて譜面を覚えさえすれば、完璧に叩けるようになる。ただ一つ注意すべきなのは、12・13小節目の連符である。厳密なタイミングは私自身つかめない場合もあるのだが、16分刻みで正確に打つと、しっかりつながることが多い。実際はややずれていると思うのだが…。。この点については、詳細がわかり次第、追ってレポートにしたいと思う。
〜中盤編〜
中盤の山場といえば、やはり27〜30小節の、以下の譜面。

初めのうちは、全部のオブジェを取ろうと思ってもうまくいかないかもしれない。そこで、慣れるまでは3・5・7番のオブジェを無視してみよう。そうすると、押し方としては左手で1番、右手で2・4・6番を担当することになる。オブジェの総数に対して無視するオブジェが少ないため、この程度の無視ならば大きな影響はない。初心者のみなさまは、ここでグルーブゲージをあまり下げすぎるとクリアはきびしい。せめて、90%は残しておきたいところである。
〜終盤編〜
拍子が変わり、オブジェラッシュが来る場面である。ただ、ラッシュといっても同時オブジェはせいぜい3〜4個程度なので、慌てずにさばけばクリアは目前である。ここでひっきりなしに落ちてくるオブジェの山にビビってしまってはいけない。落ち着いてみれば、決して叩けないオブジェ配置ではないはずである。初心者のうちは、鍵盤操作に集中するためにスクラッチを無視してもいいであろう。慣れてきたら、終盤フルコンボも夢ではない。ぜひこれを目標に頑張っていただきたい。
〜最後に…補足&連絡〜
さて、本当ならばここに楽曲の全譜面を載せたいところなのだが、諸般の理由により断念せざるを得なかった。以降のレポートでも、譜面は必要最低限の部分以外は掲載しない。どうかご理解をいただきたく思う。また、この曲の攻略レポートが見たい!というみなさま、研究所にぜひともメールをいただきたい。ただし、私も未だクリアできない「THE SAFARI」についてのレポートと、アナザー曲についてのレポートのリクエストにはお応えできません。