
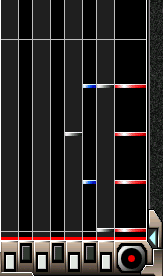
第6回 研究テーマ:クリアのためのテクニック 2001年2月8日(木)
beatmaniaをプレイする上でのテクニックにはさまざまなものがあると思われるが、その中でも楽曲をクリアする上でポイントとなってくる基本テクニックや、裏技っぽいテクニックのいくつかをここで採りあげる。
1)キー&スクラッチ
簡単に言うと、片手でターンテーブルと鍵盤を同時に押すテクニックである。これは基本中の基本であろう。これができないと、高難易度の曲ではかなりの苦戦を強いられることになる。では、どのような場合に活用すべきなのだろうか。言うまでもなく鍵盤とスクラッチが同時に流れてきた場合に、鍵盤とスクラッチを独立して取っていると間に合わないような譜面の時に利用するのだが、以下で具体的にキー&スクラッチを使う意味のある譜面パターンの基本を紹介する。

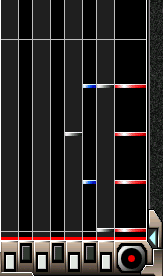
図の通り、左スクラッチの場合なら、1・2・3番の鍵盤とスクラッチを組み合わせる。右スクラッチなら5・6・7番の鍵盤を組み合わせる。即座にこのキー&スクラッチが使えるようになると、複雑なオブジェ配置にも対応しやすくなる。コツとしては、手のひらを広くかまえて、親指で鍵盤を、小指でターンテーブルをなでるように動かすこと。下の譜面をご覧いただきたい。
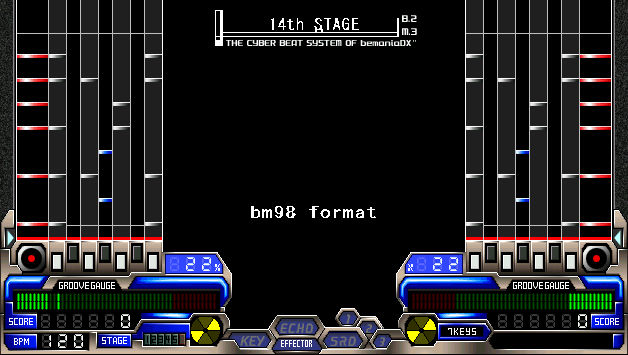
さて、この例ではかなりスクラッチ・鍵盤ともども、やや込み合った譜面となっている。スクラッチを取る上の注意点として、込み合った譜面においてはターンテーブルを同一方向に回し続けても1オブジェ分しか反応しないため、左右交互に回さなければならない。そこで、この譜面を全て取るには、鍵盤はともかくとしてスクラッチの取り方が重要になってくる。この譜面を、キー&スクラッチを使ってプレイする場合と使わないでプレイする場合とを比べてみていただきたい。また、キー&スクラッチを使ってプレイする場合、運指法はどのようになるか、自分なりにシミュレートしてみていただきたい。
2)同時押し
第5回の研究レポートでも少し触れたが、もともと階段状になっている譜面をごまかして押してしまう裏技的テクニックである。概要については前回述べているのでここでは深く触れないでおく。ただ、あくまでこのテクニックはプレイミスによるゲージ減少を少しでも抑えるためのもの、すなわち、曲クリアのみを目指すためのテクニックであって、少しでもスキルの上達を目指す人にとっては過剰に頼るべきテクニックではないということをここでお断りしておく。
3)オブジェ無視
テクニックと呼ぶのもおこがましい気がするが、その名の通り降ってくるオブジェの一部を無視してプレイすることである。この技を使う上の注意点として、無視するオブジェの数をしっかりと見極めること。あまり無視するオブジェが多すぎると、プレイは容易になるが、当然クリアは遠のく。理由はいうまでもなく、無視したオブジェにはPOOR判定が当てられるからだ。ちなみに、標準的な設定では見逃しによるPOOR判定1つにつきグルーブメーターは6%減少する。つまり、クリア目前まで100%を保っていても、最後に4つオブジェを見逃すだけでクリアを逃すというわけだ。よって、終盤で殺しにかかる曲(←終盤になって複雑なオブジェ配置がどさっと降ってくる曲)では、このテクニックを利用する際に注意が必要である。また、このテクニックのメリットは、オブジェを一部無視することで複雑な譜面を叩きやすくすることにあるので、オブジェを無視しつつも取れる譜面はきっちりと取っていかなければならない。できる限り見逃しによるゲージ減少をカバーすることが重要である。
以上のことを踏まえて、以下の譜面をご覧いただきたい。
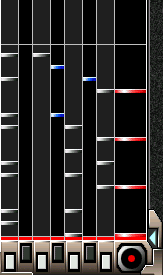
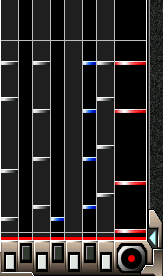
まずは左の譜面、全てを取るにはかなりのテクニックが必要である。しかし、こんな譜面でも今回の研究レポートで挙げたテクニック全てを使えば、キレイに押せなくてもたかだか6~10%のゲージの減少で済むのである。さらに右の譜面などは、同時押しとキー&スクラッチを使うだけでゲージが減るどころか、数%増えてしまう。「うわぁ、こんな譜面なんて押せないよー。。」とあきらめてみる前に、まず何でもチャレンジしてみる姿勢が大事であると思う。最初は誰だってクリアできないもの。やり方が汚いだとか、体裁が良くないだとか言って敬遠するよりも、必死にクリアを目指して頑張る姿勢こそが上達につながると、私は信じている。そして、頑張った人たちこそがいつの日か、どんな譜面でもキレイに弾きこなせるようになるであろう。その時初めて、同時押しやオブジェ無視のような外道的テクニックでも立派に役目を果たしたことになるのだ。最初から完璧を目指さず、地道に練習を重ねる…これが、全ての音ゲーに言える、最善の上達法ではないだろうか。
第5回 研究テーマ:階段押し 2001年2月6日(火)
つづいてのテーマは、beatmaniaシリーズのプレイテクニックである階段押しについてレポートする。階段押しとは、連続する隣り合うオブジェを弾きこなすことであり、ピアノ系の楽曲をプレイする上で使うことの多いテクニックである。まずは例のごとく、下のような譜面を例に挙げて説明する。
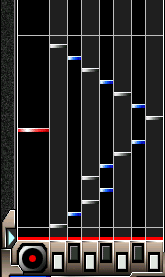
このような16連符があった場合、ひとつひとつのオブジェを人差し指1本(他の指である可能性もあるが)でさばききるのは困難である。やはりここは、ピアノを弾きこなす要領で5本の指(両手を使うなら10本だが)を駆使してさばくのが正当であろう。このような階段押しの基本として、まず必要なことは鍵盤の感覚を覚えることである。鍵盤ボタンを見ないでも、即座に各オブジェに対応する鍵盤が押せるくらいにまで慣れていれば、マスターも容易になろう。一番基本的な階段押しとして、白鍵盤を親指、青鍵盤を人差し指で押し、あとは手を置く位置をずらすことで対応する方法が考えられる。上の例では、右手だけで鍵盤を押すことを前提にすれば、押し方の一例として「右親→右人→(右手ずらし)→右親→右人→右親→右人→(右手ずらし)→右親→右人→左手(スクラッチ)→右親→(右手ずらし)→右人→右親→(右手ずらし)→右人→右親→(右手ずらし)→右人→右親」などが考えられる。少々慣れてくれば、黄色の手間を省くために、スクラッチ直後の右親を中指で押すなどといった方法もあり得る。
つまるところ、階段押しの方法として、これといって定義されているものはなく、各プレイヤー自身の押しやすい方法を、プレイを重ねる上で開発していくのがよい。攻略記事等にある運指法などは参考程度にしておいて、やはりまずは自分なりの方法を持つ方が上達につながると思う。ただ、できることならばなるべく10本全ての指を駆使できるような方法を利用した方がよい。10本の指全てがスムーズに動くように練習を重ねれば、上級者への道はすぐに開けるであろう。
最後に、「階段押しなんかできねぇよ!ふんっ!!」といじけているあなたへ。以下の譜面で、かなり反則っぽい方法を伝授したいと思う。
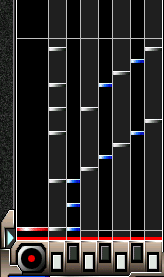
さてこの譜面、知ってる人なら知ってる、とある楽曲の譜面の一部分なのだが、いわゆるリズムパートと階段押しが複合している場面で、16分の階段押しの部分を無理やり8分で押してしまうわけである。そのために、隣り合う白鍵盤と青鍵盤を同時押ししてさばいてしまうのである。つまり、実際の譜面は上の通りなのだが、押し方としては下右図のように押すことになる。
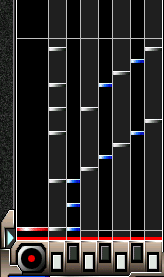 →
→ 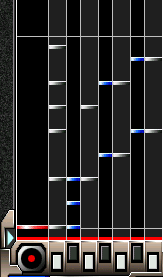
成功させるポイントとしては、できればハイスピードプレイの方がよい。理由は、研究レポート第2回を読んでいただければご理解いただけるであろう。このような反則チックな攻略法については、次回に詳しくレポートしてみたいと思う。願わくは、このようなテクニックに頼らず、正当法でチャレンジしていただきたい。
第3回 研究テーマ:右スクラッチと左スクラッチ 2001年2月5日(月)
ⅡDXの筐体は、1P側と2P側で鍵盤の配列が違う。1P側は鍵盤の左方にターンテーブルがあるのに対し、2P側は鍵盤の右方にターンテーブルがある。よって、まったく同じ曲を1P側と2P側とでプレイする場合、多少なりとも難易度に差が出てくるはずである。今回は、左スクラッチと右スクラッチとで難易度的に変わってくる場合を採りあげてみよう。
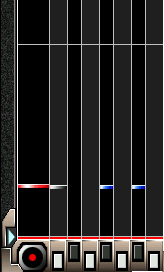
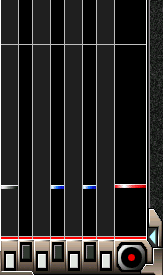
上の図を見ていただきたい。このようなオブジェ配置がある場合、右スクラッチと左スクラッチではどのように対処すべきであろうか。どちらの場合も、片手で3つの鍵盤をさばける人ならば何ら問題は生じないのだが、普通は左スクラッチの場合は、左手でスクラッチと白鍵盤を押し、右手で残りの青鍵盤2つをさばくであろう。右スクラッチならば左手は白鍵盤と青鍵盤(左)を押し、右手で青鍵盤(右)とスクラッチを押す。この二つのやり方を比べると、どちらかといえば左スクラッチの方が両手の動きに無理が少ないように思える。もちろん、この鍵盤配置が左右反転すれば右スクラッチの方が有利である。
この通り、オブジェ配置によって同じ曲でも1P側プレイと2P側プレイで難易度は変わってくる。それではいったい、1P側でプレイするのと2P側でプレイするのとではどちらがより有利なのだろうか?これは、大きな差はないと言える。1P側に特に有利な曲、2P側に特に有利な曲という比較方法で全ての曲をチェックしてみても、割合的には半々であり、また1P側でしかクリアができない(もしくはその逆)という曲も今のところ発見されていない。すなわちプレイヤー自身が練習を積むことで、どの曲でも必ずクリアに適した運指法が見つかるということである。この運指法が1P側と2P側の場合で大きく変わってくる場合に、難易度の差として現れてくるのである。
プレイしていて、「何だかこの曲は指がしっくり動かないなぁ…」と思った場合は、ミラーモードで一度プレイしてみてはどうだろう。ミラーモードとは、鍵盤配置が左右反転するモードである。以下では、上と同じ譜面をミラーモードにした場合である。運指方法がどう変わるか、どちらが有利であるか、みなさんで考えてみていただきたい。(左がオリジナル譜面、右がミラー譜面である)
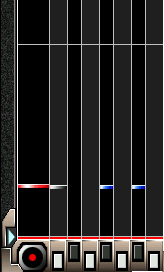
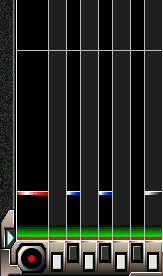
第2回 研究テーマ:ハイスピードプレイ 2001年2月4日(日)
曲自体のスピードは変えず、オブジェの降るスピードだけを2倍にしてプレイできるモードを、ハイスピードプレイという。このハイスピードプレイ、初心者には敬遠されがちなのだが、実はかなり優れたオプションプレイなのである。ここではこのハイスピードプレイについて論じてみることにする。
まず、ハイスピードプレイ第一の利点は、曲自体のスピードを変えずにオブジェのスピードを2倍にするため、元の譜面よりもオブジェ間隔が広がる点である。これはすなわち、込み合った譜面であってもハイスピードプレイをすることによって多少間隔の空いた譜面になるため、プレイしやすくなるということである。以下に、ノーマルスピードの場合の画面表示と、同じ曲をハイスピードにした場合の画面表示を図示しておく。いかに譜面が見やすくなるかおわかりいただけるであろう。
次に、オブジェに対する反応神経が養える点である。オブジェのスピードが普通の2倍になるのだから、当然オブジェが画面内に表示される時間は1/2になる。つまり、同時に画面に現れるオブジェの情報量は必然的にハイスピードの方が少なくなるわけである。これにより、ハイスピードプレイの方がより速くオブジェに反応しなければならない。これは、初見の曲に強くなるための訓練につながる。事実、やまきはハイスピードプレイを使うようになってから、初見クリア率が格段に上がっている。
さらに、ハイスピードプレイの方がより高得点を狙えるという説がある。これは、オブジェに対する判定の方法が、時間差で行われていることから理解できる。beatmaniaでは、オブジェが画面下部の判定ラインに達したときにタイミング良く鍵盤を押すとそれに対する判定がオブジェごとに評価されるが、その基準は、判定ラインと鍵盤操作との時間差がどれだけ開いているかによっている。つまり、2倍のスピードでオブジェが落ちているということは、判定の幅も通常の2倍に広がっていることを意味するのだ。これにより、ノーマルプレイよりもさらにGREAT率がアップし、高得点が出せるということになる。
以上、ハイスピードプレイの利点をいくつか挙げてみたが、当然短所も存在する。まずは何といっても、初めのうちはスピードの速さについていけないことであろう。こればかりはしばらくハイスピードでプレイしまくって、慣れていただくより他に対処法はないであろう。次に、判定幅が広くなる(←実際には幅が広がっているわけではなく、ハイスピードプレイによって我々がそう感じているだけであるが)ことから、込み合った譜面での空打ちによるBAD評価が出やすくなることである。しかし、以上の短所を踏まえてもなお、ハイスピードプレイの良さは損なわれない、とやまきは断言できる。初心者の方のステップアップとして、しばらくはノーマルプレイで譜面を覚え、慣れてきたらハイスピードプレイに切り替えてスキルアップを目指すという方法が望ましいであろう。ぜひ、ハイスピードプレイでチャレンジしていただきたい。
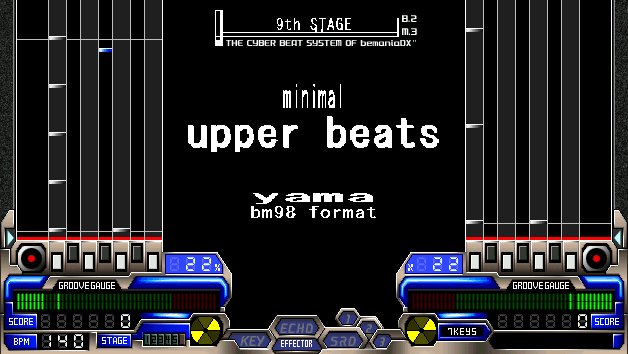
↑<図1>ノーマルスピードとハイスピードの違い
1P側(画面左)がノーマルスピードプレイ、2P側(画面右)がハイスピードプレイ。ノーマルスピードでは画面内に1小節がしっかり表示されているのに対し、ハイスピードでは小節の半分程度しか表示されない。オブジェ間隔が2倍になるため、ハイスピードの方が譜面が見やすいことは、この図から明らかであろう。
第1回 研究テーマ:目押しとリズム 2001年2月3日(土)
初めてbeatmaniaをプレイされる方なら誰もがそうだと思うが、画面上部から降ってくるオブジェを目だけでタイミングを取って押す方法、これを、私は「目押し」と呼んでいる。この「目押し」という方法は、BG音量の小さい筐体でプレイするには適した方法といえるが、ある程度上達した中級者以上の方はできるだけ目押しで攻略するのを避けてプレイした方がいいであろう。
その根拠としてまず第一に挙げておきたいのが、リズムに乗ることでよりいっそうゲームにのめり込める点である。かと言って、人が大勢いるゲームセンターの中で、体全体でリズムを取りながらbeatmaniaをプレイするというのも傍から見ていてかなり恥ずかしいものなので、せいぜい足で密かにリズムを取るとか、そして慣れてきたら頭の中でBPMをつかみ、リズムに乗るよう心がけてみよう。こうすれば光GREAT率もかなりアップすることと思う。
このリズム感の修練において、必要不可欠なのがBG。BGのリズムに素早く乗ることが大切である。そのため、練習する筐体はできるだけBG音量の大きいものを選ぶべきである。上達するためには筐体選びから。この程度の手間を惜しんではダメである。なお、BG音量を上げる方法としてはエフェクターを活用する方法が一般的である。また、近頃は曲の途中でBPMが変わるというとんでもない曲や、BPMがめちゃくちゃ早い曲も多数出ている。特に前者は、目押し攻略がやや難しいため、これらの曲が苦手だっ!!という方々はぜひ、リズム押しをマスターしていただきたい。
最後に、「どうしてもリズム押しがマスターできない!!オレにはどうせリズム感なんてないんだよ…(涙)」といじけている方へ。リズムのつかみやすいテクノ系の曲で練習を積んでみてはいかがでしょう?元来リズム感の全くない人はいないと思うし、何よりもリズム押しでパーフェクトプレイを達成したときの感動を一人でも多くの方に味わっていただきたい。beatmaniaを心から愛している目押しプレイヤーのみなさまは、ぜひbeatmaniaのサントラ盤を聴きまくってリズムマスターを目指してほしい。
(注:やまきは別にコナミのまわし者ではございません…)